本記事では、お守りの捨て方を解説します。
大切にしてきたお守りをどうやって処分したらいいか、気持ちの整理がつかずに手放せない人も多いはず。
- 「古いお守りはゴミに出していいの?」
- 「遠方の神社まで返納しないとだめ?」
上記のような疑問や不安に向けて、神聖な縁起ものならではの捨て方をご紹介します。心置きなくお納めして、新たな生活に踏み出しましょう。
お守りの捨て方4選
早速、気になるお守りの捨て方をご紹介します。以下4つの方法を、それぞれ見ていきましょう。
- 寺や神社へ返納する
- 一般ゴミで処分する
- どんど焼きなどで焚き上げてもらう
- 不用品回収業者に依頼する
順番に解説していきます。
寺や神社へ返納する
お守りは、基本的にいただいた寺や神社に返納するのが、最も自然な方法です。
多くの神社や仏閣では、古くなったお守りを納める古札納所が設けられています。年末年始や節目の時期に返した経験がある方もいらっしゃるでしょう。
郵送での返納を受け付けているところもあるため、遠方の場合でも安心して返納できます。返納先は、元の授与場所が望ましいとは言え、他の神社や寺でも問題ありません。きちんとお礼の気持ちを込めて返納すれば、縁起が悪くなることはないのです。
一般ゴミで処分する
神社や寺に行けない場合、一般ゴミで処分する方法もあります。
お守りの分別自体は、「燃えるゴミ」として捨てられるケースがほとんどですが、大切なのは、処分する時の気持ち。
お守りに、「今まで守ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。その後、半紙や白い紙に包み、塩を軽くふって清めてから処分するのをおすすめします。
宗教的な意味合いに配慮しながら処分すれば、一般的な燃えるゴミとは一線を画するため、心もすっきりするはずです。
どんど焼きなどで焚き上げてもらう
地域によっては、正月の行事として「どんど焼き」や「左義長」と呼ばれる火祭りが行われます。
前年の正月飾りや熊手、書き初めなどと一緒に、お守りやお札を焚き上げてもらえます。どんど焼きは神聖な火で清める意味があるため、古いお守りを感謝とともに手放せる適切な方法と言えるでしょう。
持ち込める品目が決められている場合もあるため、事前に地域の開催情報や持ち込み方法を確認しておくと安心です。
不用品回収業者に依頼する
お守りが大量にあったり、神社や寺に持って行く時間がない場合は、不用品回収業者に依頼するのもおすすめの方法です。
多くの業者では、お守りやお札のように神聖な品を丁寧に扱い、最終的に寺社などで供養してから処分しています。また、自宅まで回収に来てくれるため、移動や仕分けの手間もかからない安心感もあります。
なにより、お守り以外の縁起物などもまとめて引き取ってもらえるため、処分に悩むアイテムや引っ越しや断捨離時に便利に活用できる方法です。
お守りの捨て方に関する注意点
処分方法をチェックしたところで、お守りを捨てる時の注意点も見ていきましょう。
- 自宅の庭で「お焚き上げ」しない
- お守りを分解しない
- お守りを譲渡しない
上記3点を詳しく解説するので、参考にしてください。
自宅の庭で「お焚き上げ」しない
お守りはお焚き上げするイメージがありますが、自宅の庭などで勝手に「お焚き上げ」してはいけません。
自宅で燃やすと、火事のリスクがあるだけでなく、ご近所とのトラブルや違法行為につながる恐れがあります。
そもそもお焚き上げとは、神社や寺で、神仏に感謝の気持ちを込めて供養しながら焼却する神事であり、専門的な知識や安全な設備が必要な行為。
自宅で処分を検討するなら、自分で燃やさずに可燃ゴミに出しましょう。白い紙や布に包んで、感謝の気持ちを込めてから手放せば、お焚き上げに引けを取らない処分方法になるはずです。
お守りを分解しない
お守りを処分する際に、分解するのもやめてください。
お守りの中には神仏の力が宿るとされていて、縫い込まれた中身は、神職以外が見たり触れたりしないのが暗黙の決まり。勝手に開く行為は、「ご利益を無にする」「神様を怒らせる」と考えられています。感謝の気持ちを込めてそのままの形で手放しましょう。
分別すべきだという考え方は、お守りに関しては当てはまりません。処分の際も、包んでごみに出す、または神社や寺へ返納するなど、丁寧な扱いが求められます。
中身が気になるからと好奇心で開けてしまうと、逆に気持ちが落ち着かず、罪悪感を覚える結果になってしまいます。
お守りを譲渡しない
お守りは、基本的に自分のために授けてもらうもので、他人にゆずるのは避けたほうが良いとされています。
持ち主以外が使うと、効果が薄れる、もしくは意味をなさなくなるという考えが一般的。また、神社や寺ごとに祭神や宗派が異なるため、その人に合わないものを渡してしまうリスクもあります。
特に、金運や縁結びなどの個人的な願いが込められたお守りを、所持したのちに他人に渡すのは無礼と言えるでしょう。どうしてもお守りをプレゼントしたい場合は、相手のことを考えたうえで新しく授与してもらうのがマナーです。
既に手元にあるお守りは、必ず自分で処分するのを徹底してください。
お守りを手放すタイミング【捨て方と同時にチェック】
ここで、お守りを手放すタイミングをお伝えします。
基本的なお守りを手放すタイミングは、授かってから一年が目安とされています。これは、神社や寺が授与するお守りに一年間のご加護が込められている、という考え方に基づいています。
一年を過ぎると効果が切れるというわけではありませんが、感謝の気持ちを込めてお返しする行為で、区切りをつける意味が生まれます。
また、合格祈願や安産祈願など、特定の目的が達成された場合も、返納するタイミングとして適していると言えるでしょう。
長く手元に置いておけば気持ちのやすらぎの手助けになりますが、役目を終えたお守りは、きちんと感謝を込めて手放すのが、丁寧な対応なのです。
お守りを納める時のおすすめの捨て方は不用品回収業者
最後に、お守りを納める方法としておすすめの、不用品回収業者のメリットをお伝えします。
- 処分方法に悩まなくて済む
- 他の不用品もあわせて回収してもらえる
- 自宅まで引き取りに来てもらえる
上記3点、それぞれ参考にしてください。
処分方法に悩まなくて済む
神聖に扱うべきお守りは、むやみに捨てるのがはばかられるアイテム。そのような利用者のニーズを汲み、お焚き上げや神社での供養代行を請け負っている不用品回収業者も存在します。
自分で処理する手間や精神的負担を軽減できるうえ、適切にお守りを納められるので、心身ともに安心できるでしょう。複数の場所で入手したお守りも、まとめて回収してくれます。
適正に処理してくれる第三者に依頼できると、お守りのようなセンシティブな品の処分も心強いですね。
他の不用品もあわせて回収してもらえる
お守りだけでなく、古いお札や破損した縁起物など、神社関連で処分に迷う物品も、一緒に回収してもらえるのも大きなメリット。
お守りと同様、願をかけたり縁起をかついだりする品は、やはり適切に処分しないと気持ちが休まりません。だからといって、一つひとつに手間をかけていられないのも現実。
不用品回収であれば、別々に処分する手間が省けて効率が良い一方で、気持ちよく手放せる回収方法を実施してくれます。
実家じまいや遺品整理も、安心してお任せできるでしょう。
実家の片付けや遺品整理も気にかかる方は、以下記事を参考にしてください。
自宅まで引き取りに来てもらえる
お守りを大切に思う気持ちはあれど、日々の雑務でなかなか時間を取れない方も少なくないでしょう。
忙しい現代人にとって、自宅まで不用品を引き取りに来てくれるサービスは非常に便利。遠方の神社に持参する手間や、地域の廃棄ルールを調べて分別する手間も不要です。
さまざまな事例の場数を踏んでいるスタッフが、丁寧に対応してくれるため、直接返納しない罪悪感も軽減できます。
スムーズかつ安心してお守りを納められれば、心機一転、新たな門出にもつながるでしょう。
お守りは不用品回収で丁寧な捨て方を!
お守りの気になる捨て方について、お納め方法や注意点などをご紹介しました。
自分の身を守ってくれたお守りは、感謝の想いを大切にしつつも、日常に寄り添ったお納め方法がおすすめ。お守りだけでなく、扱いに悩んでいた縁起物や古いお札などは、丁寧に回収してくれる不用品回収業者を活用すると良いでしょう。
業者選びに迷ったら、ぜひ「粗大ゴミ回収・不用品回収・ゴミ屋敷清掃パイオニア!粗大ゴミ回収サービス」に、お気軽に問い合わせてみましょう。古いお守りを適切に納めて、新しい生活を送る手助けをしてくれますよ!

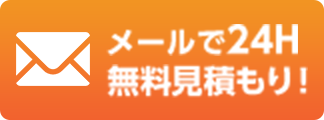
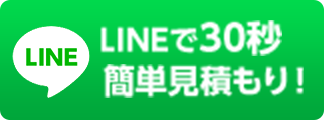

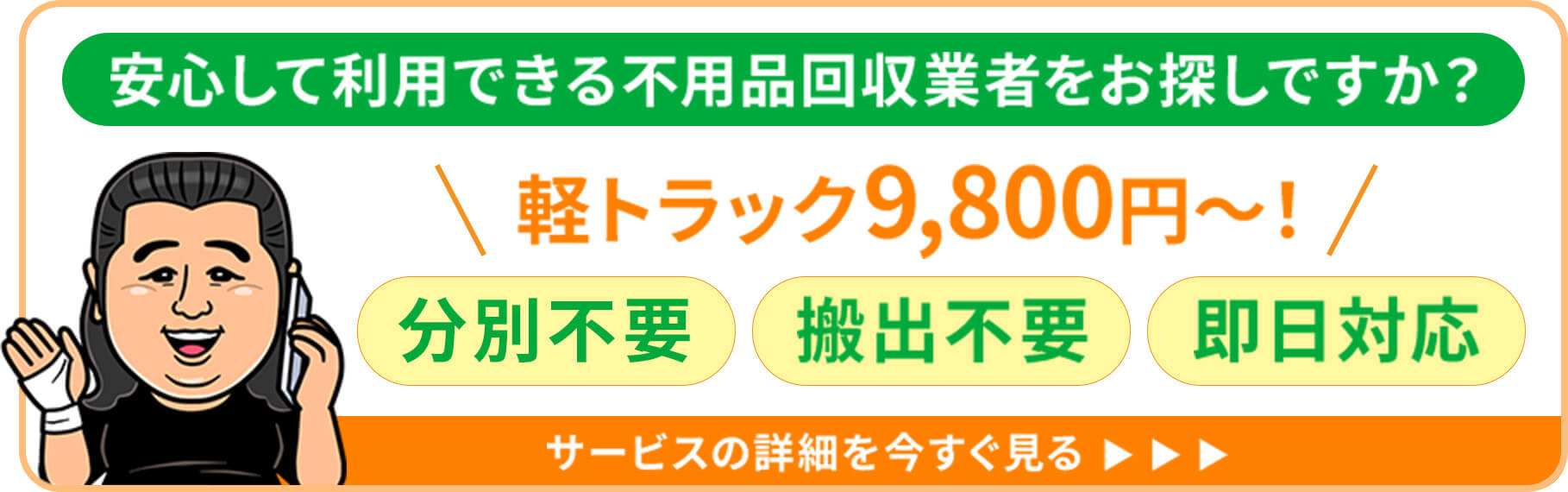












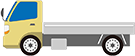







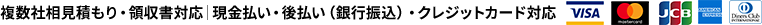
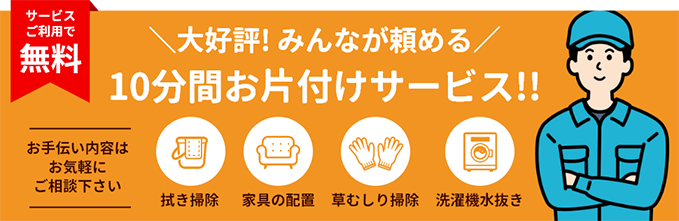
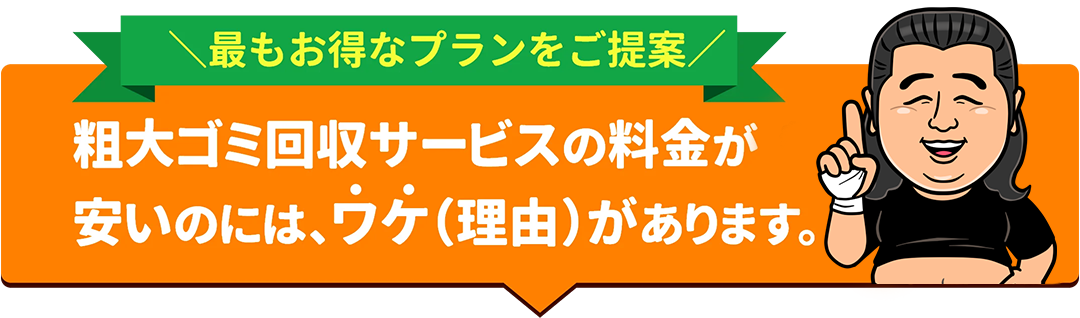



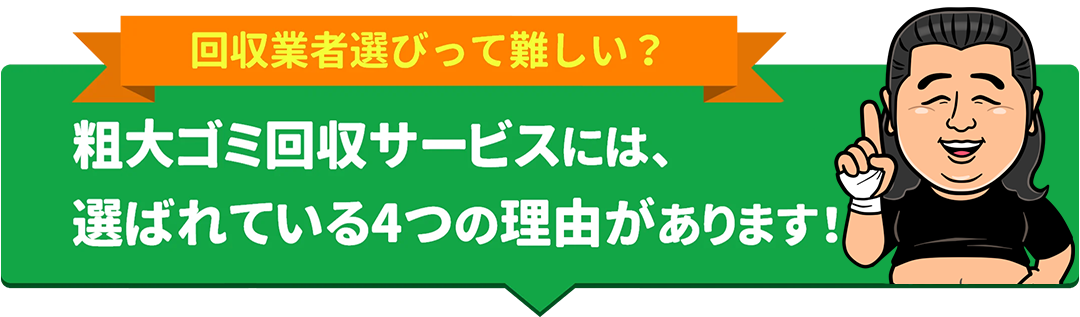





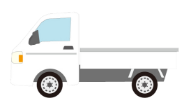



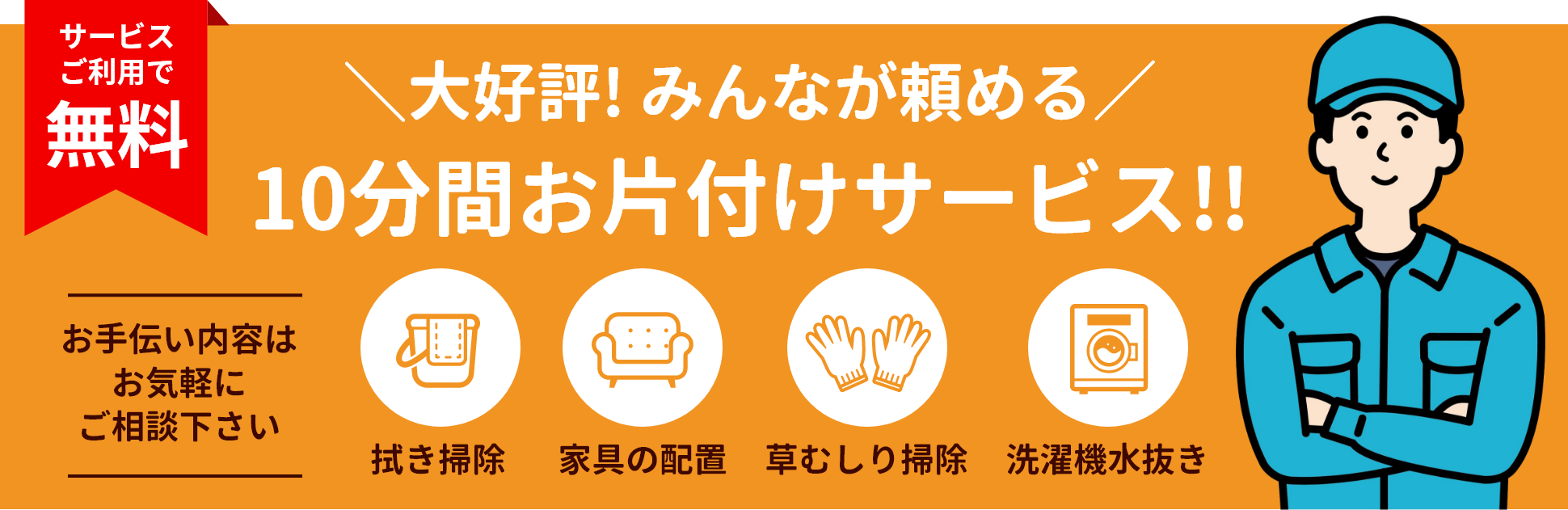
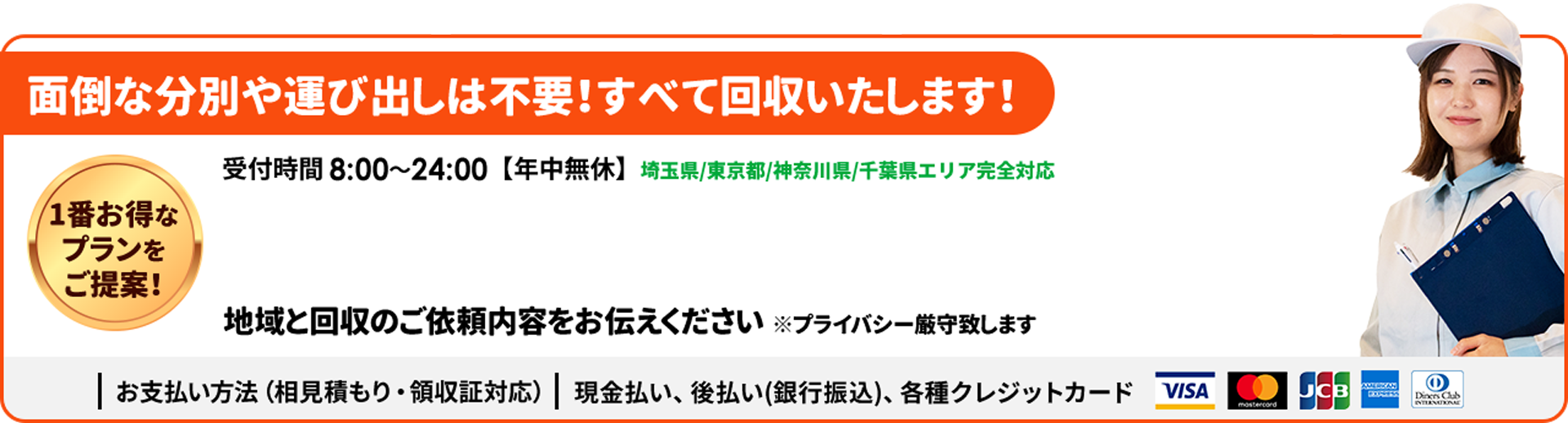
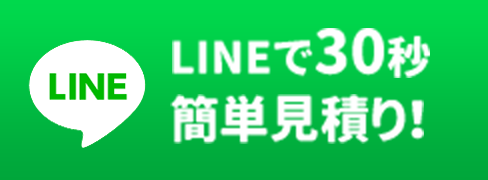
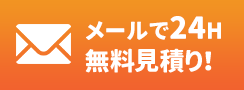













































 回収サービス
回収サービス
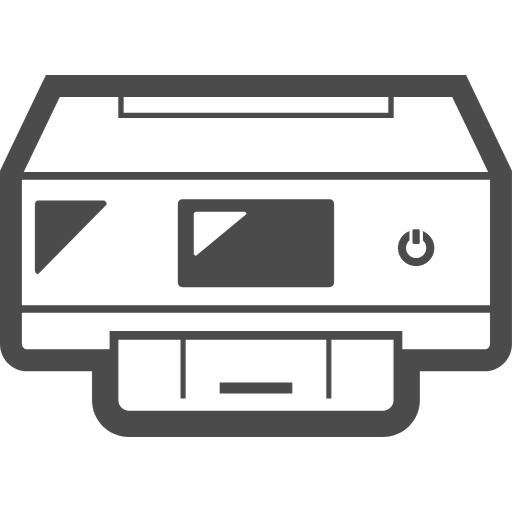
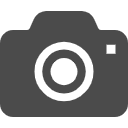
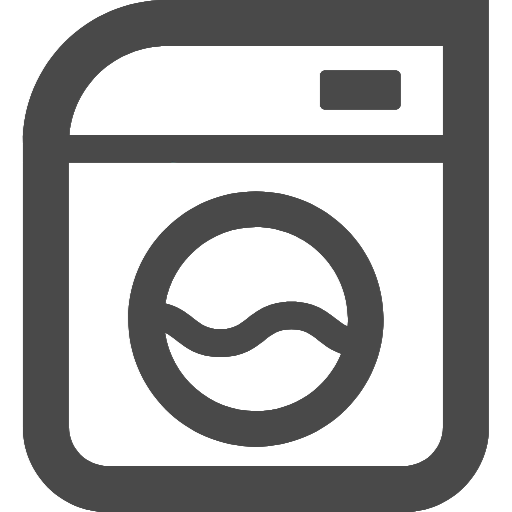
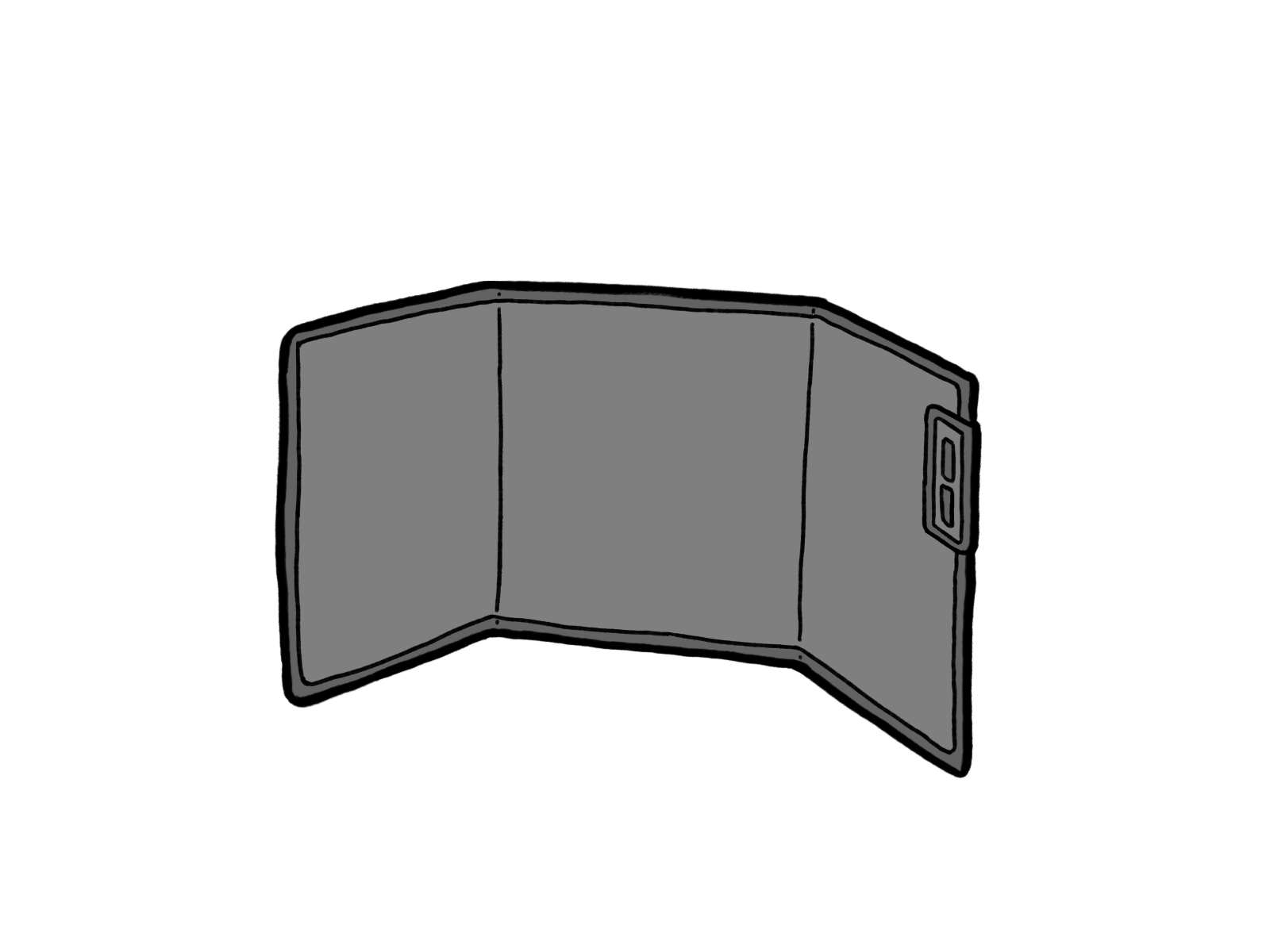
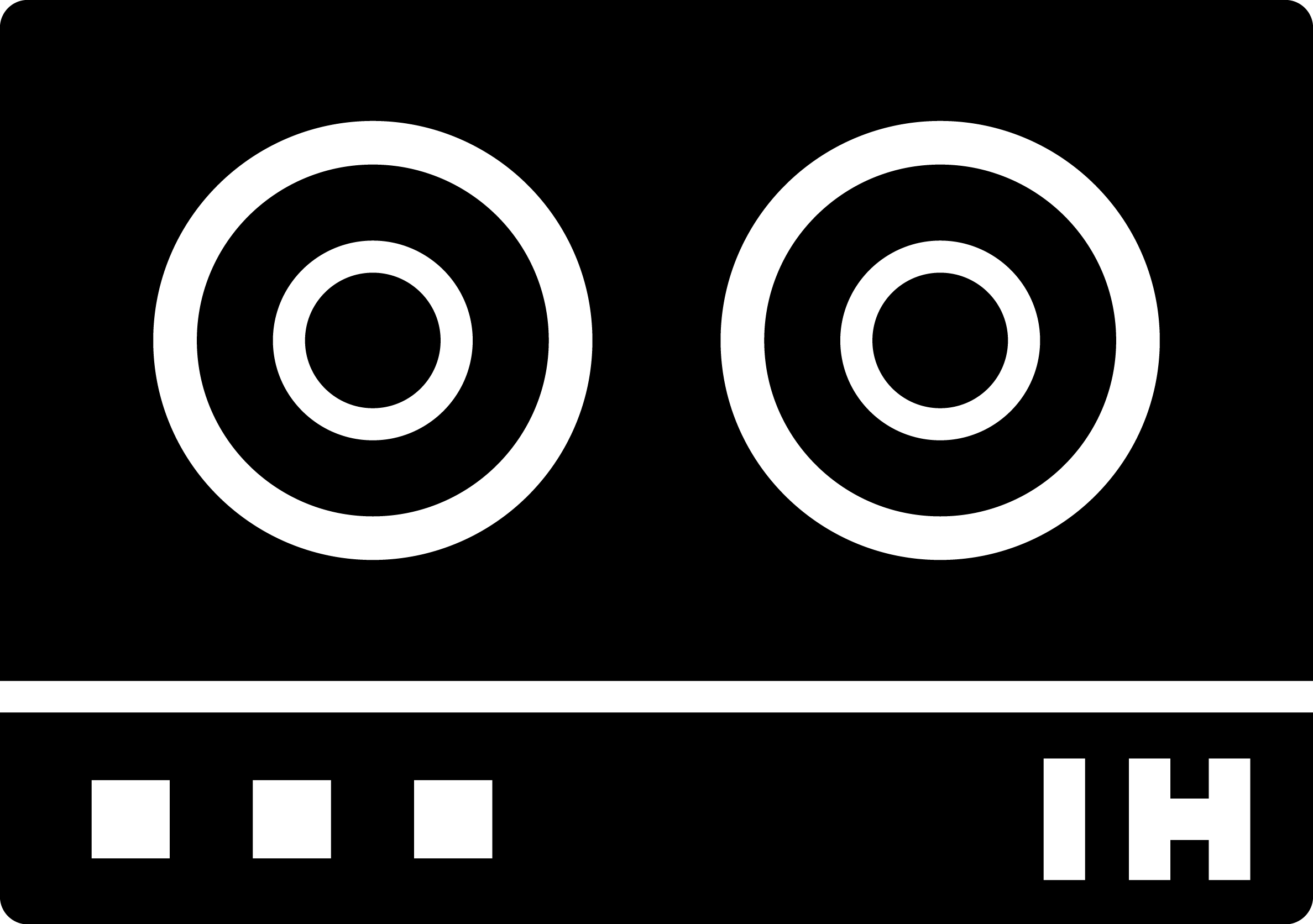
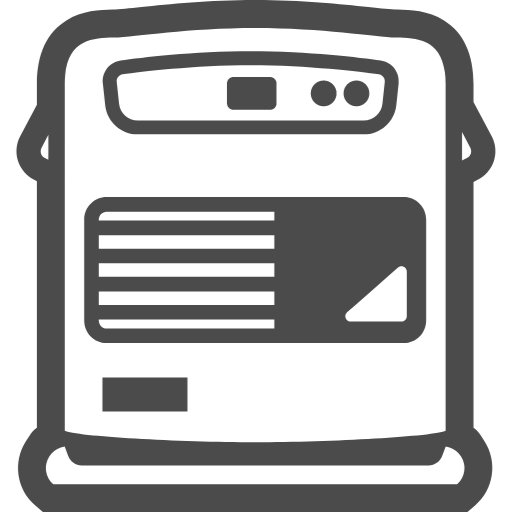
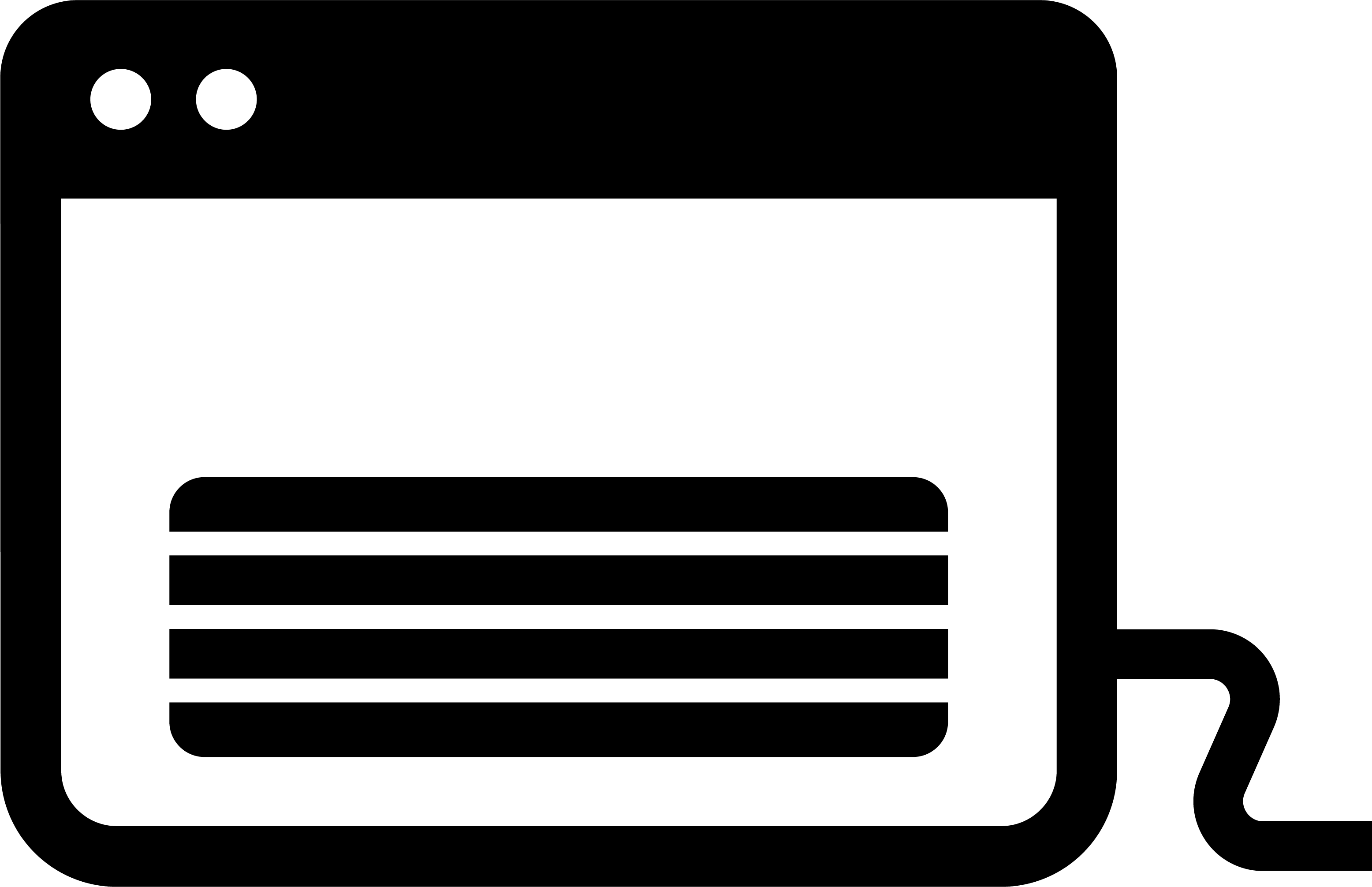
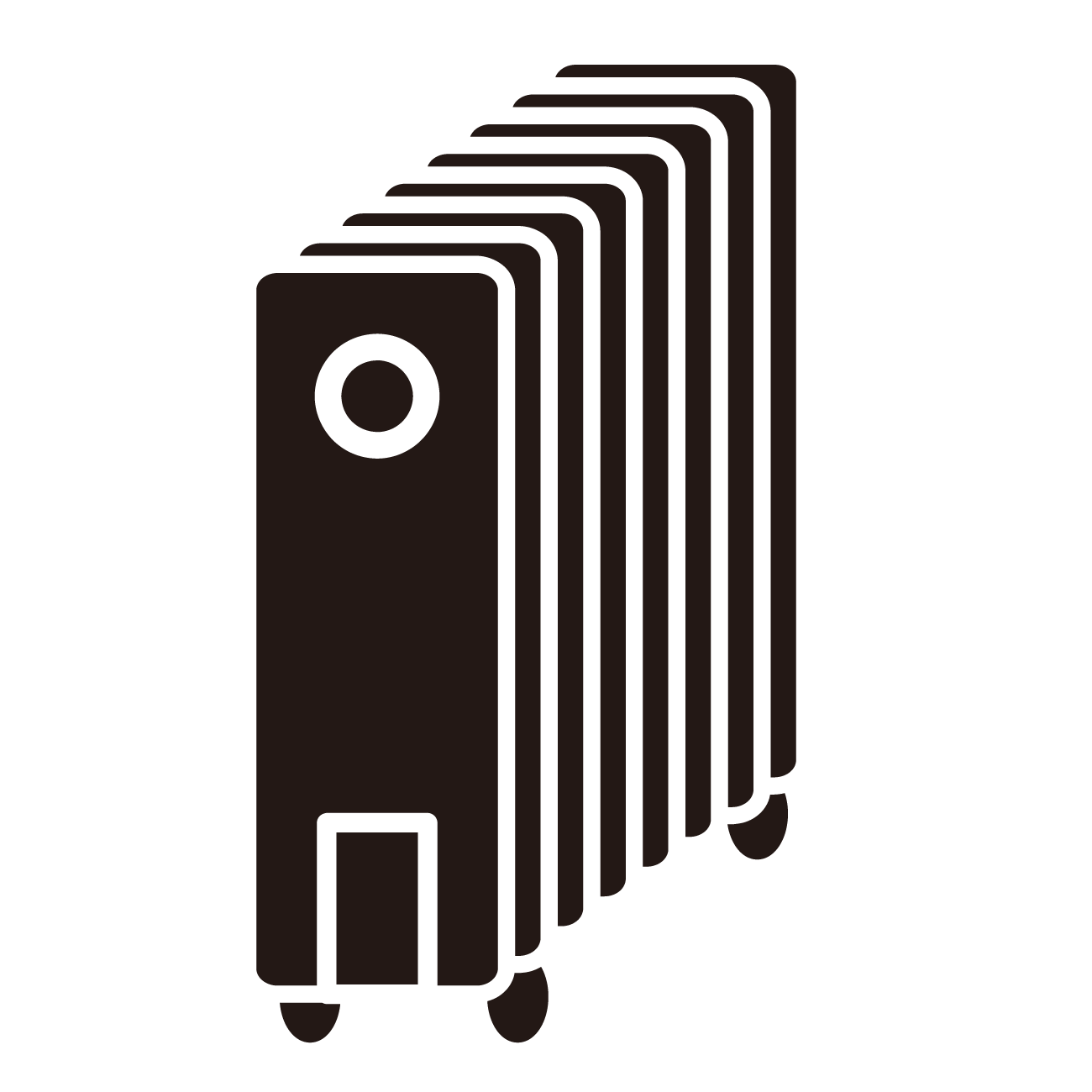
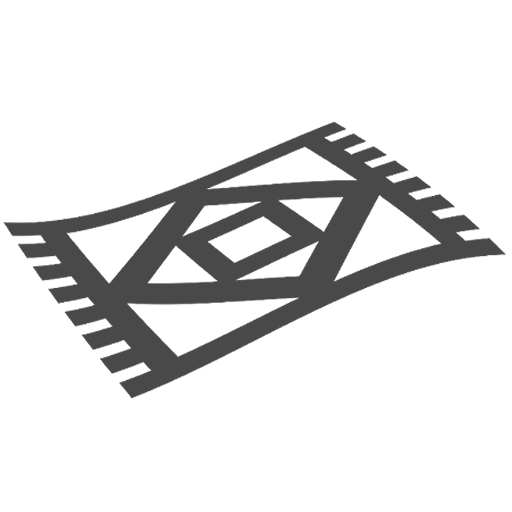
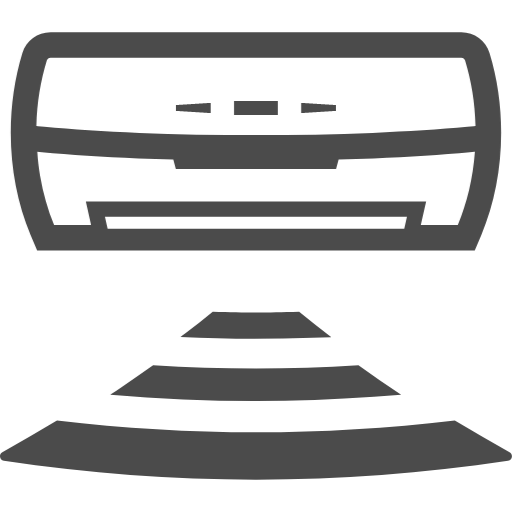
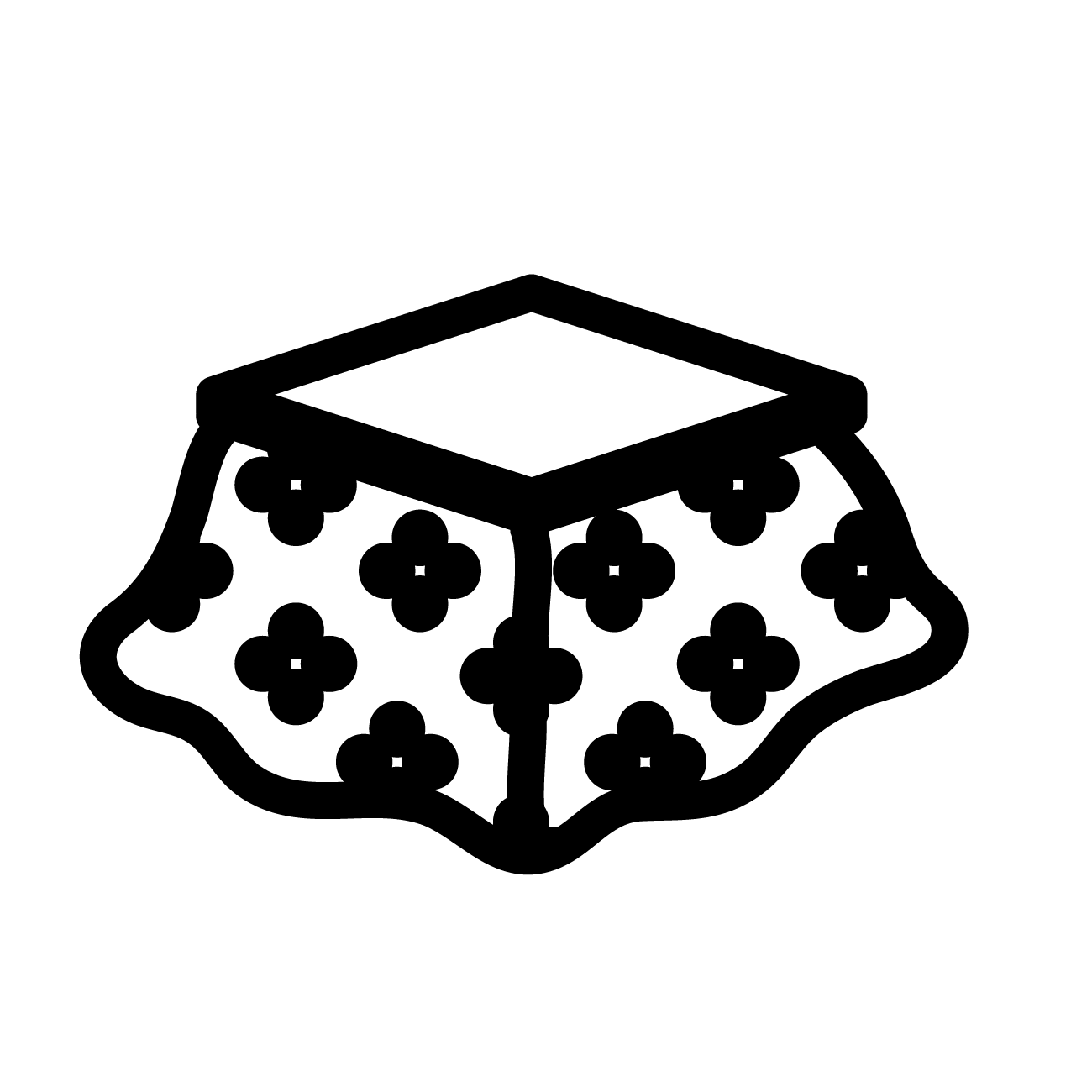
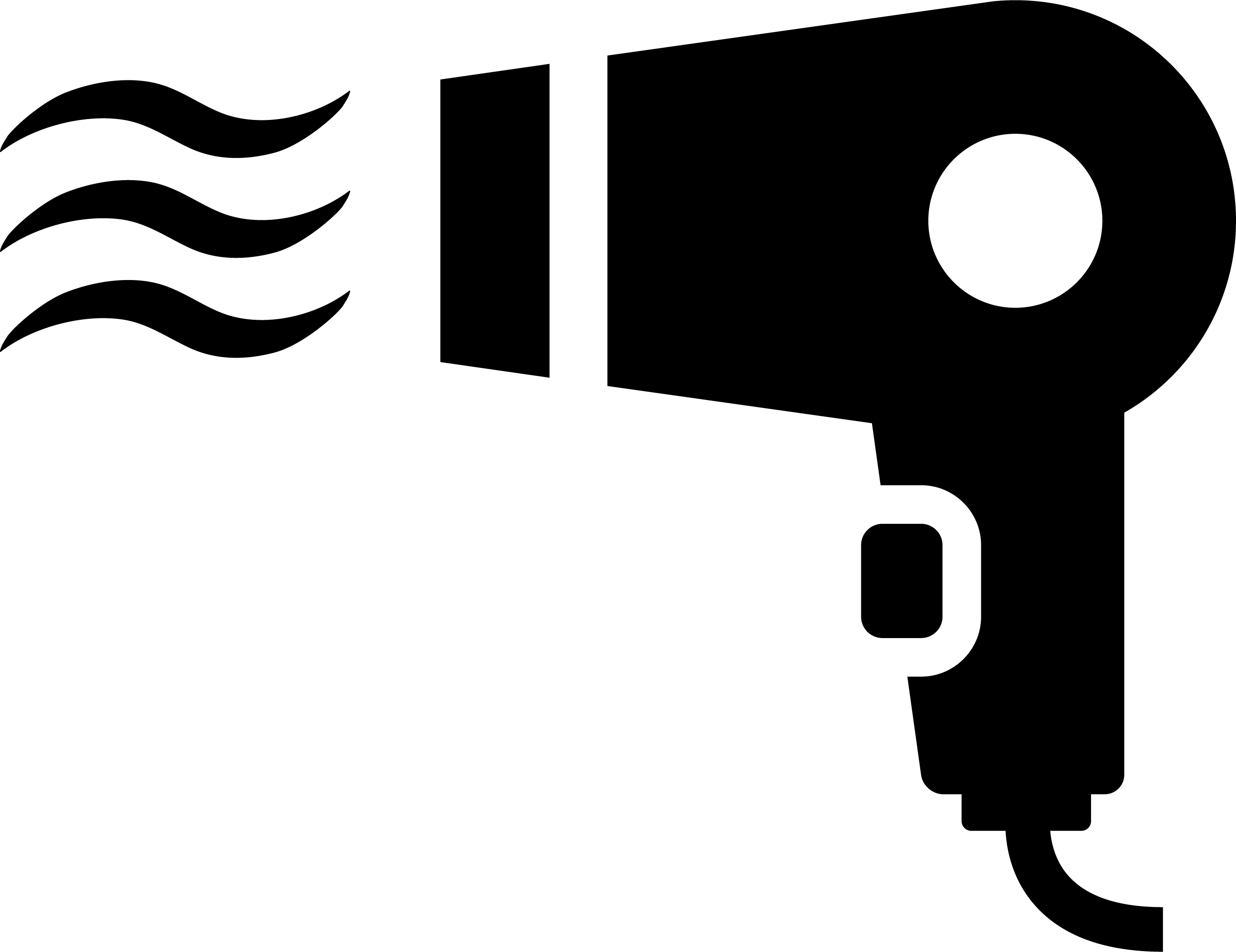
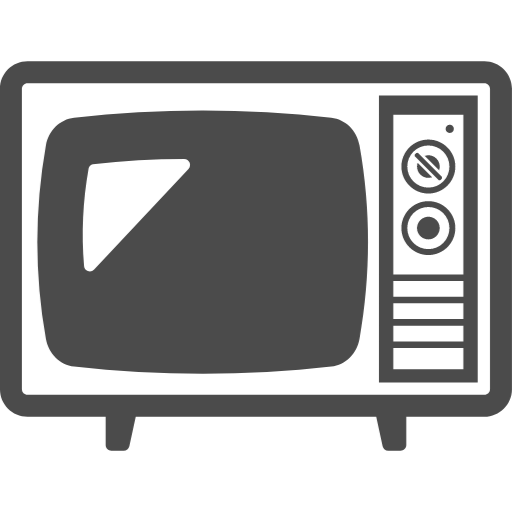
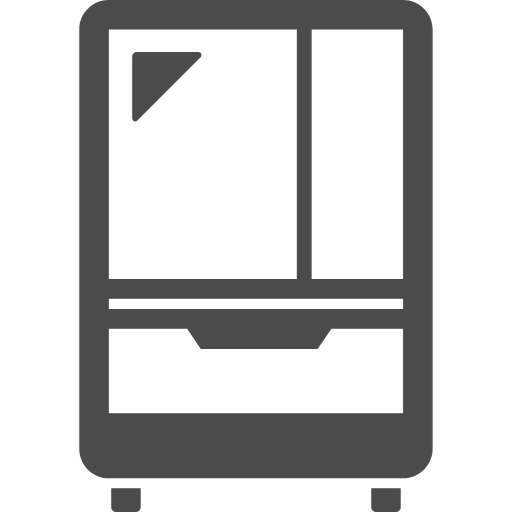
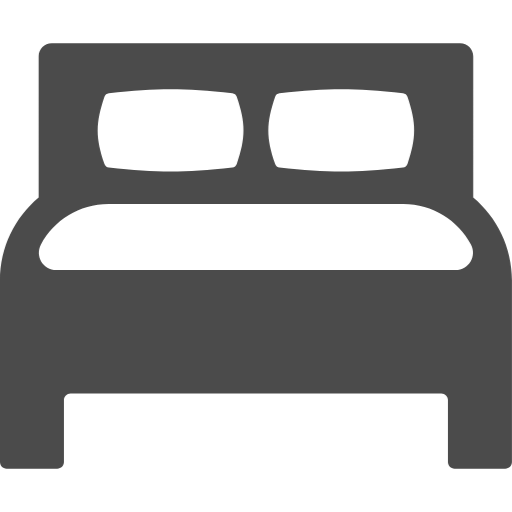
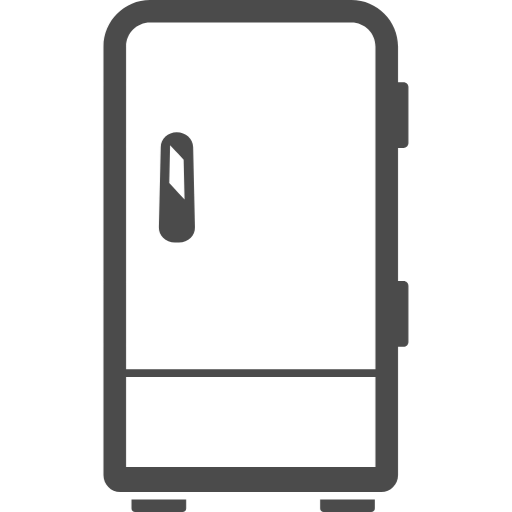
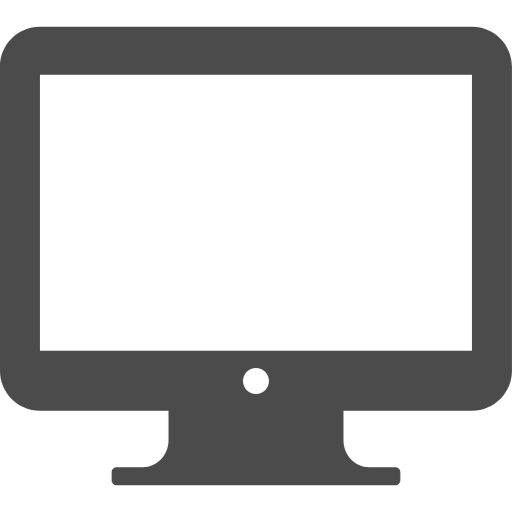
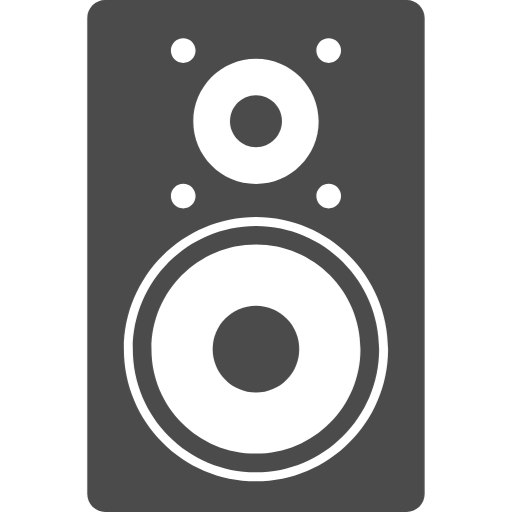
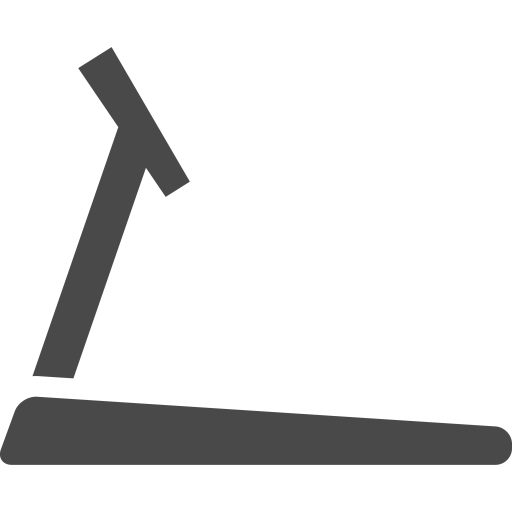
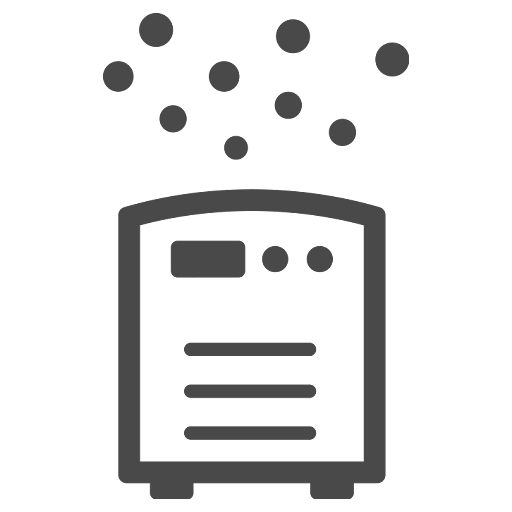
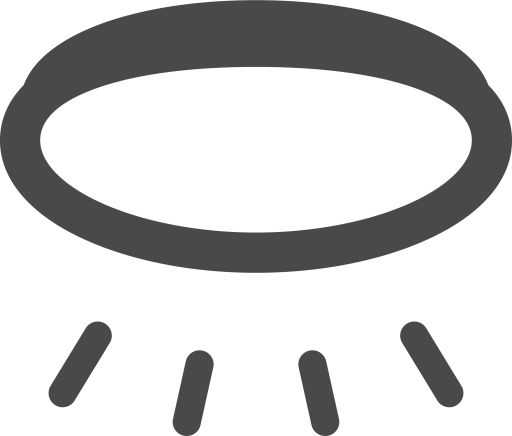

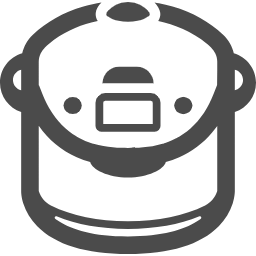
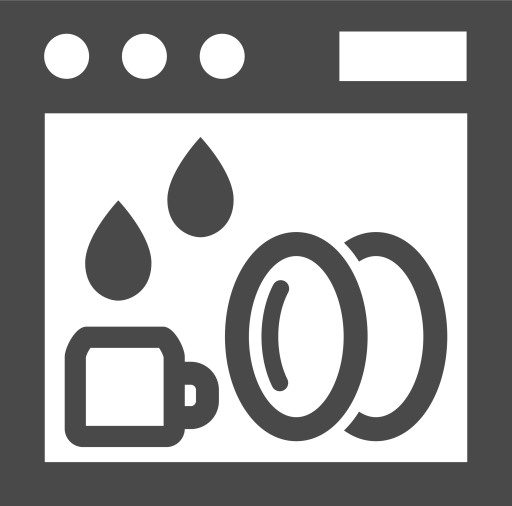
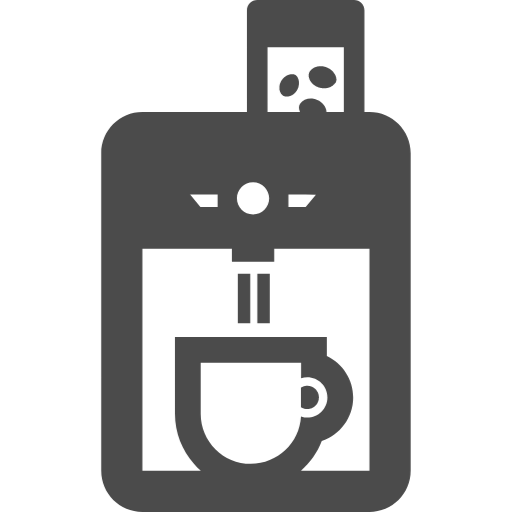
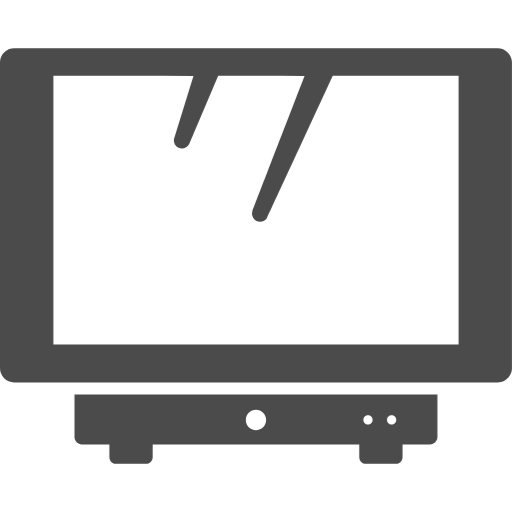
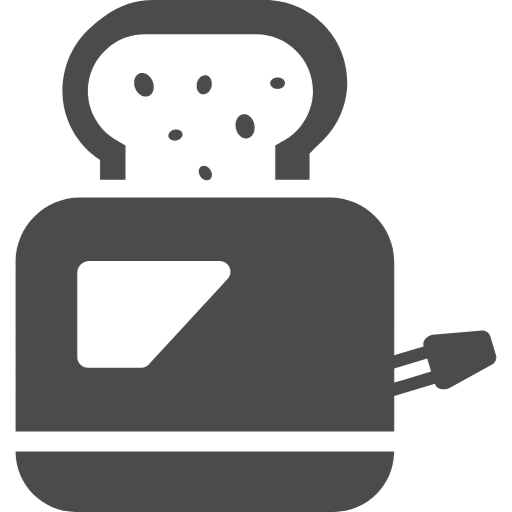
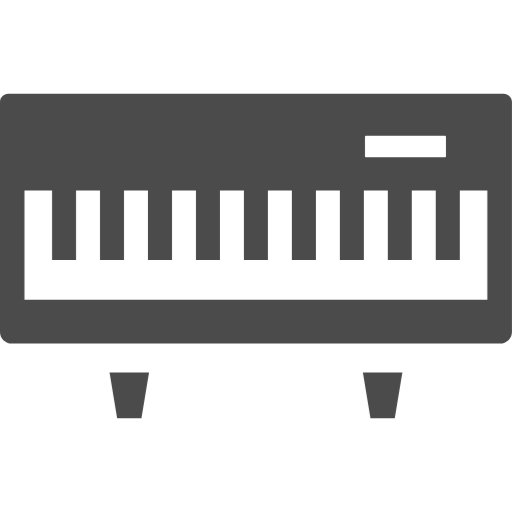
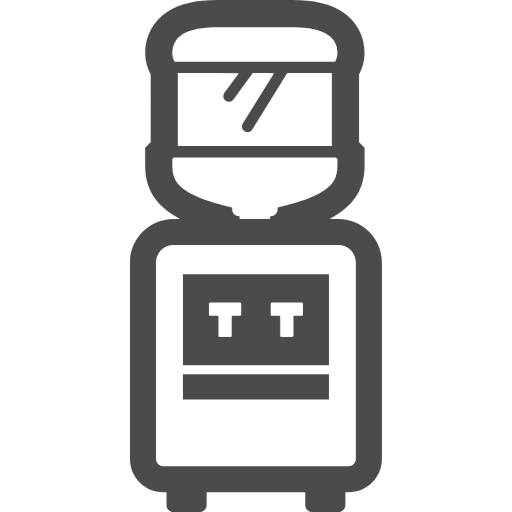
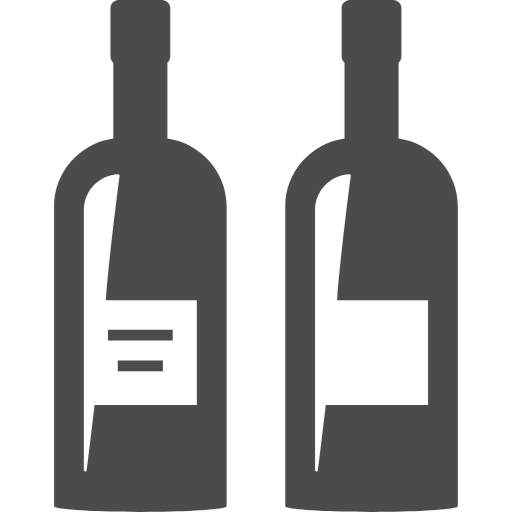
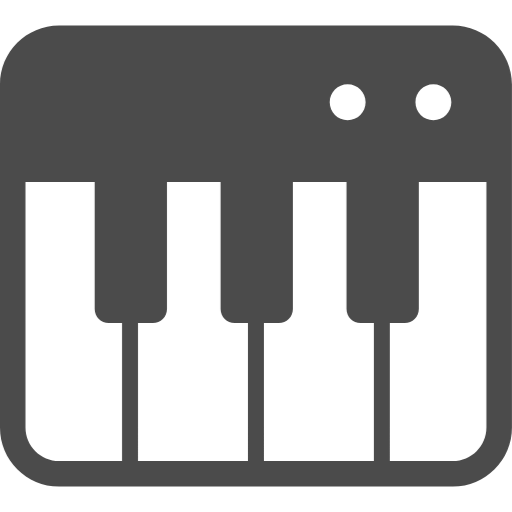
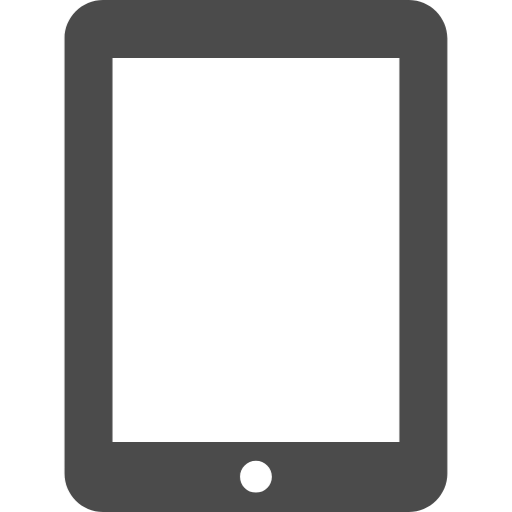
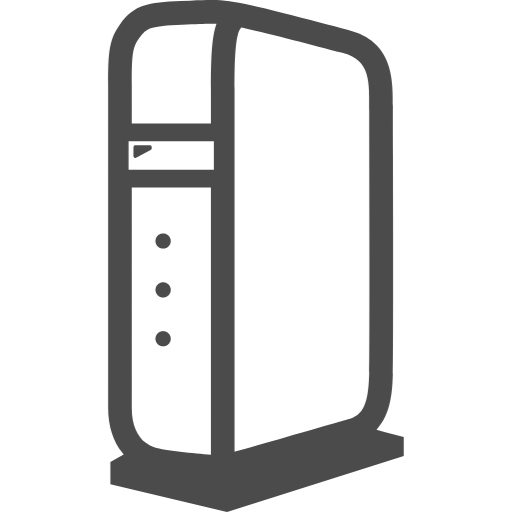
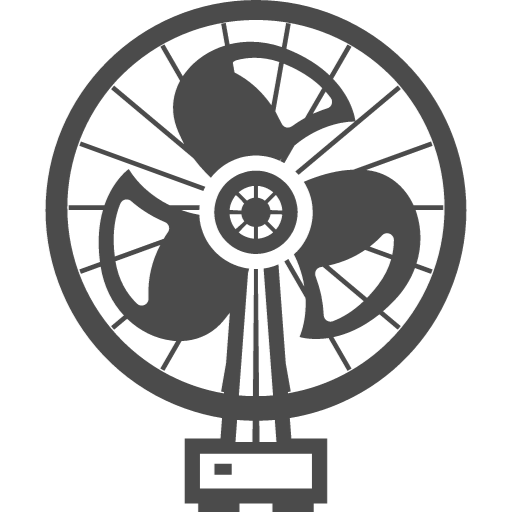

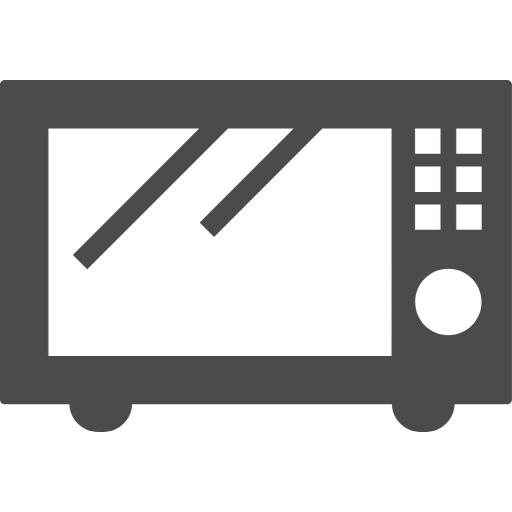
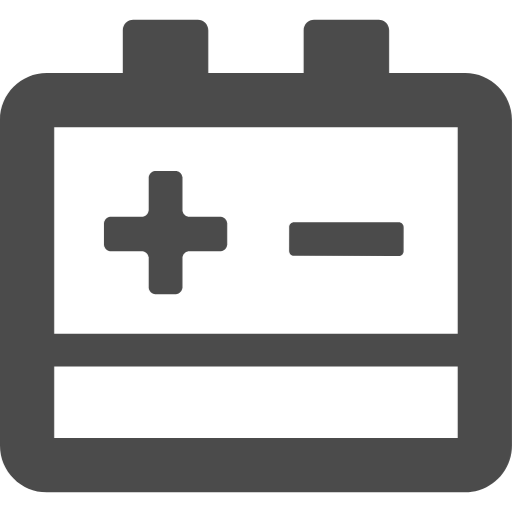
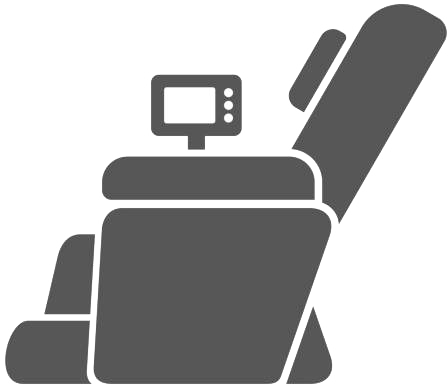
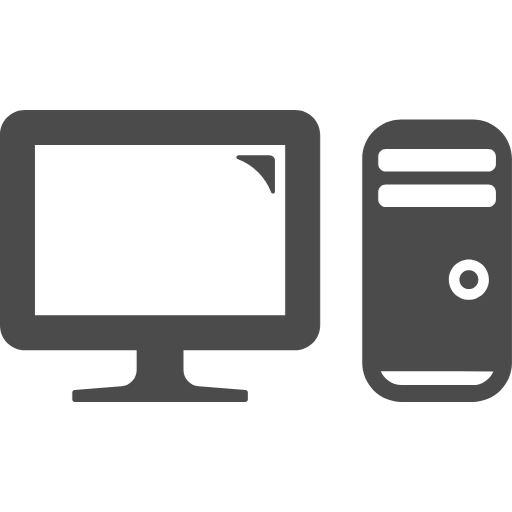

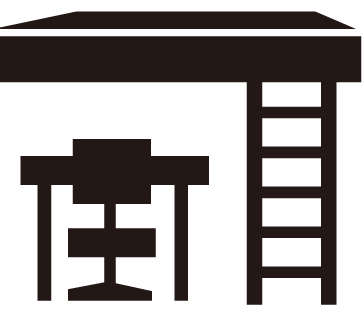
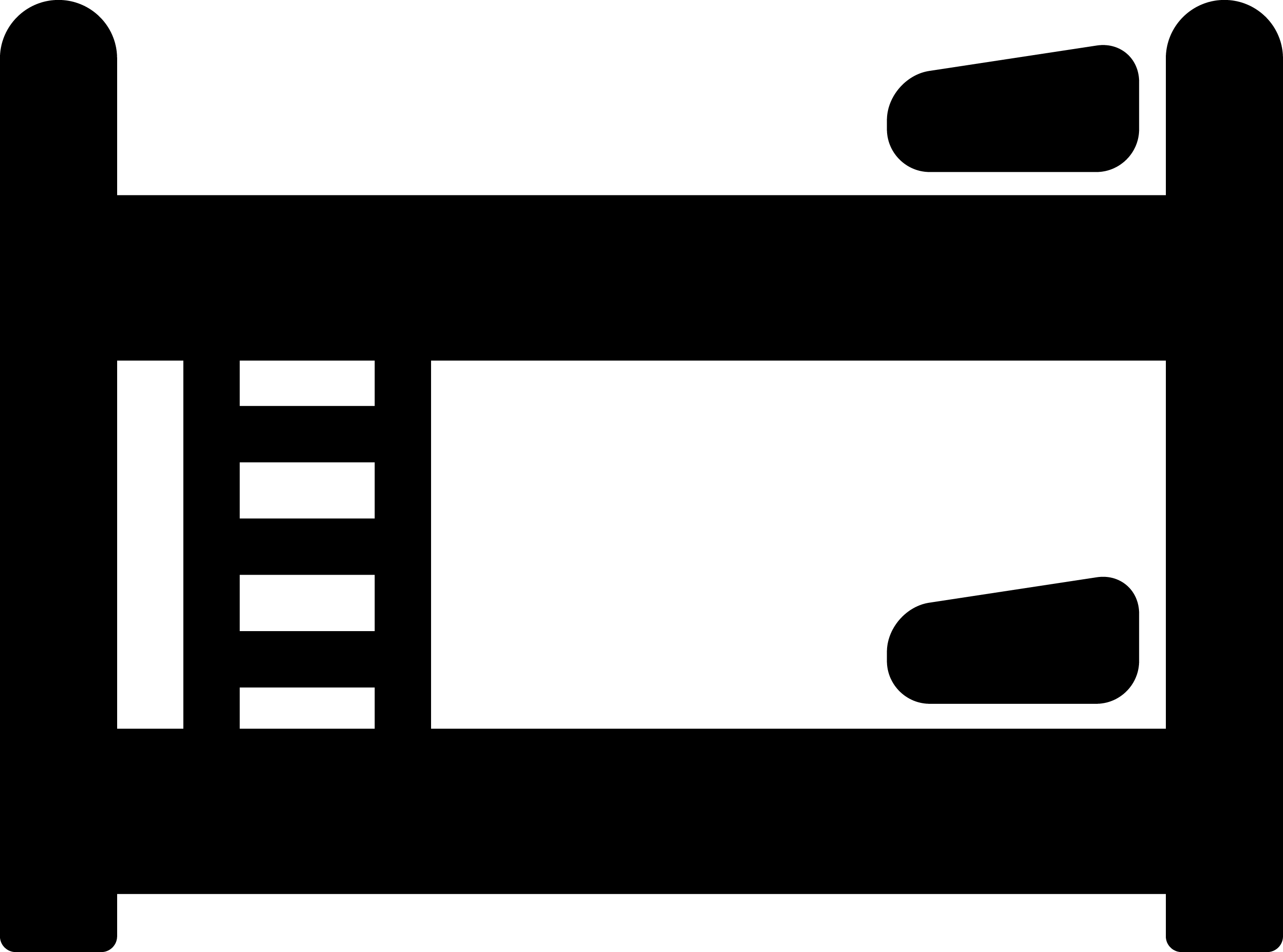



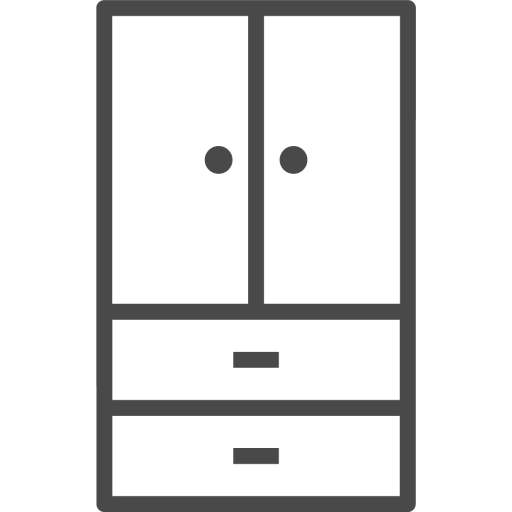
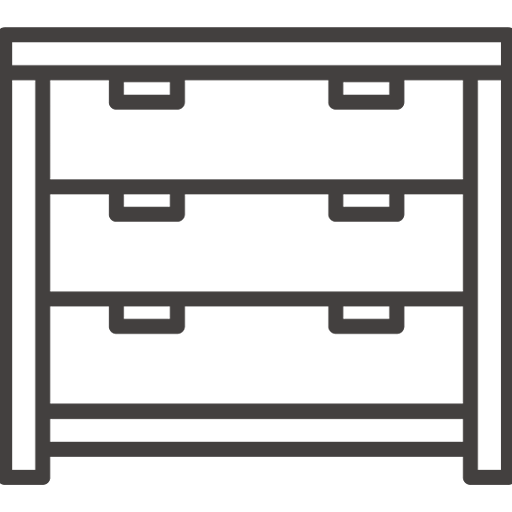
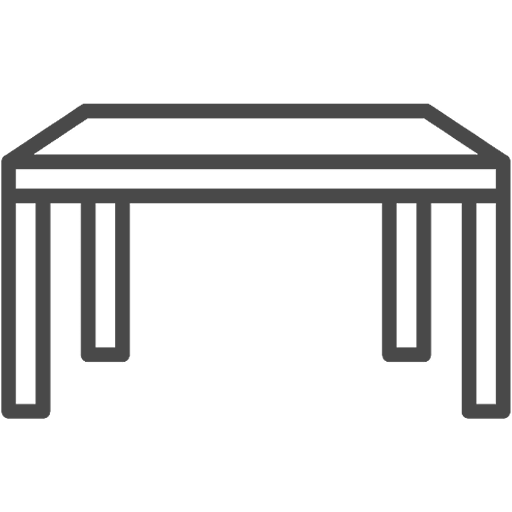


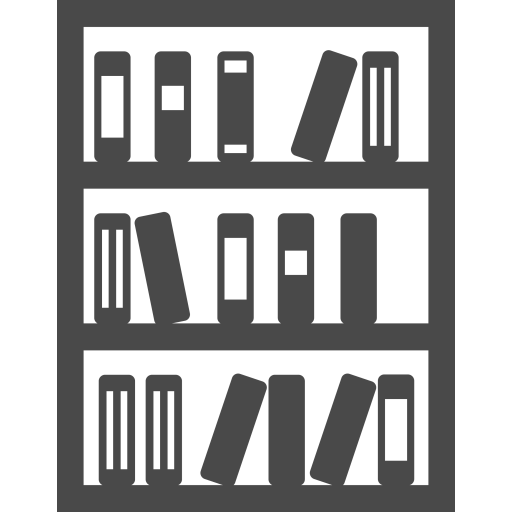
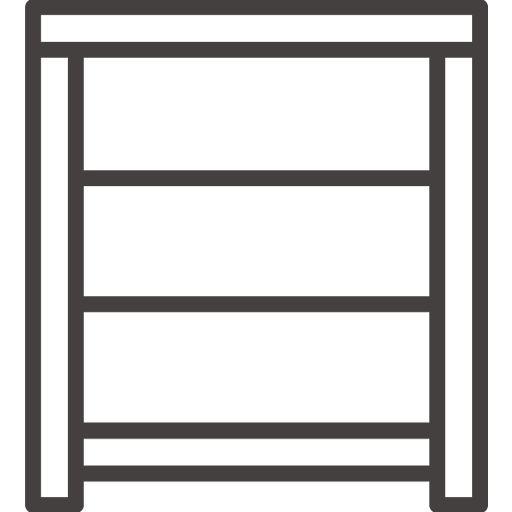
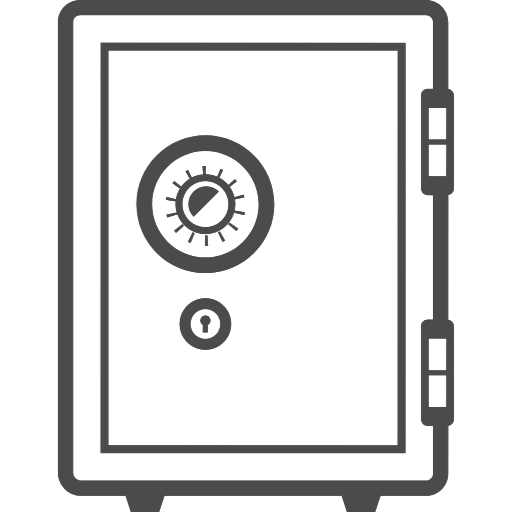
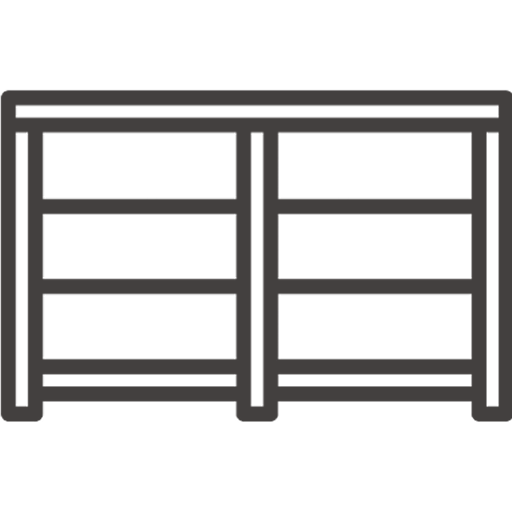

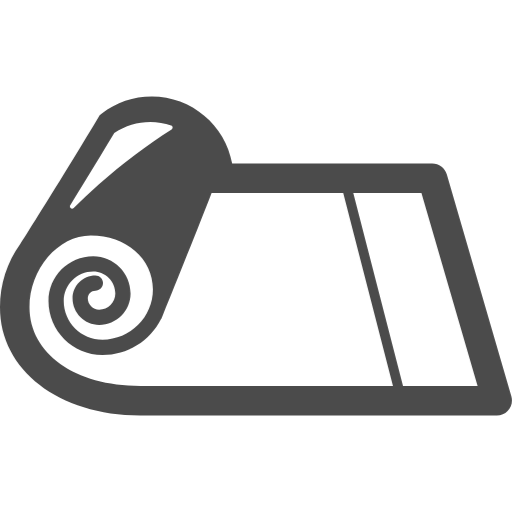
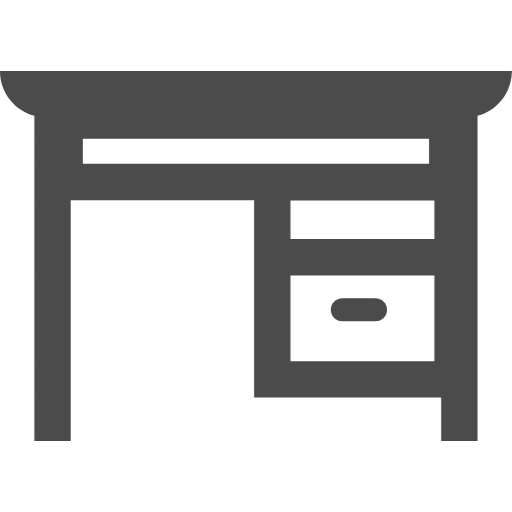
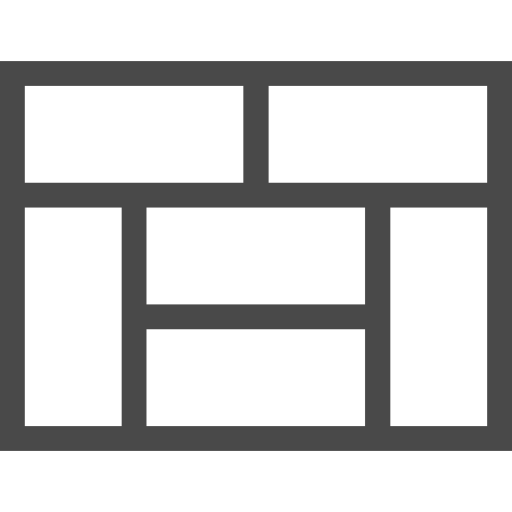
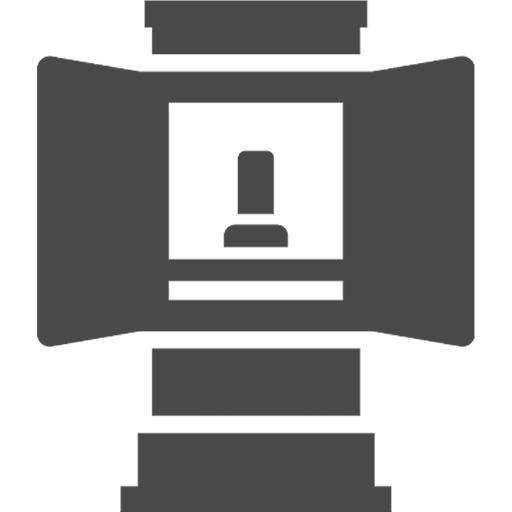
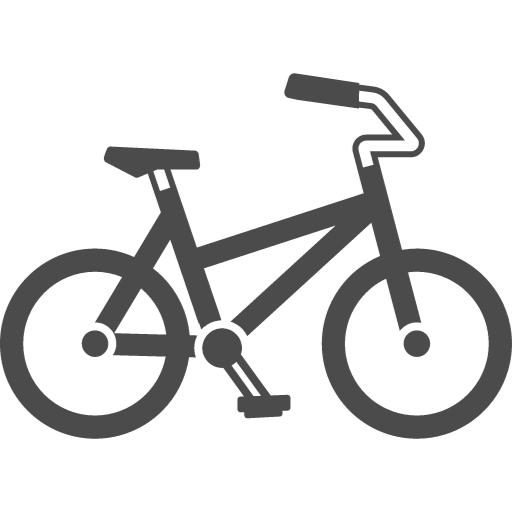
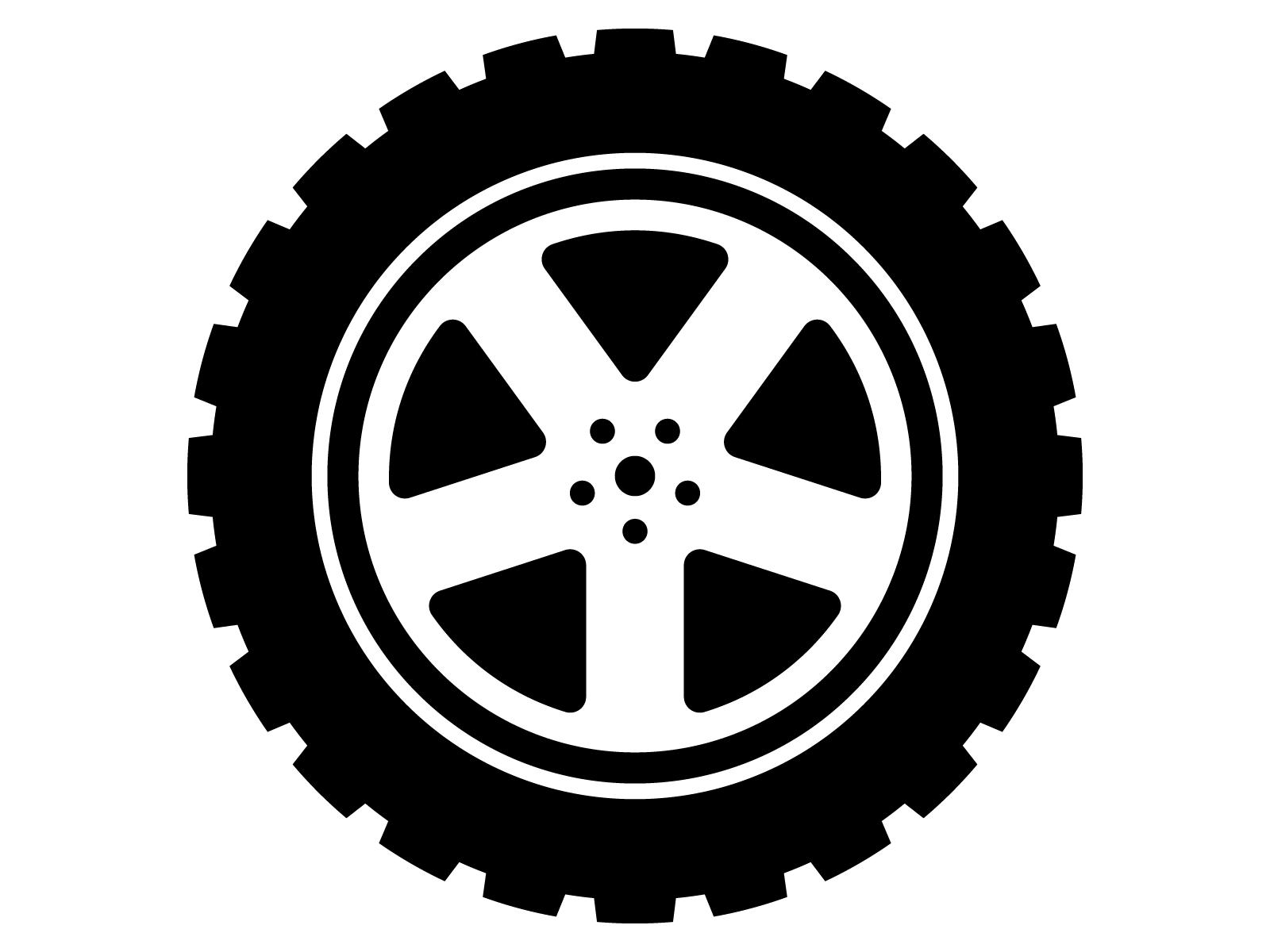
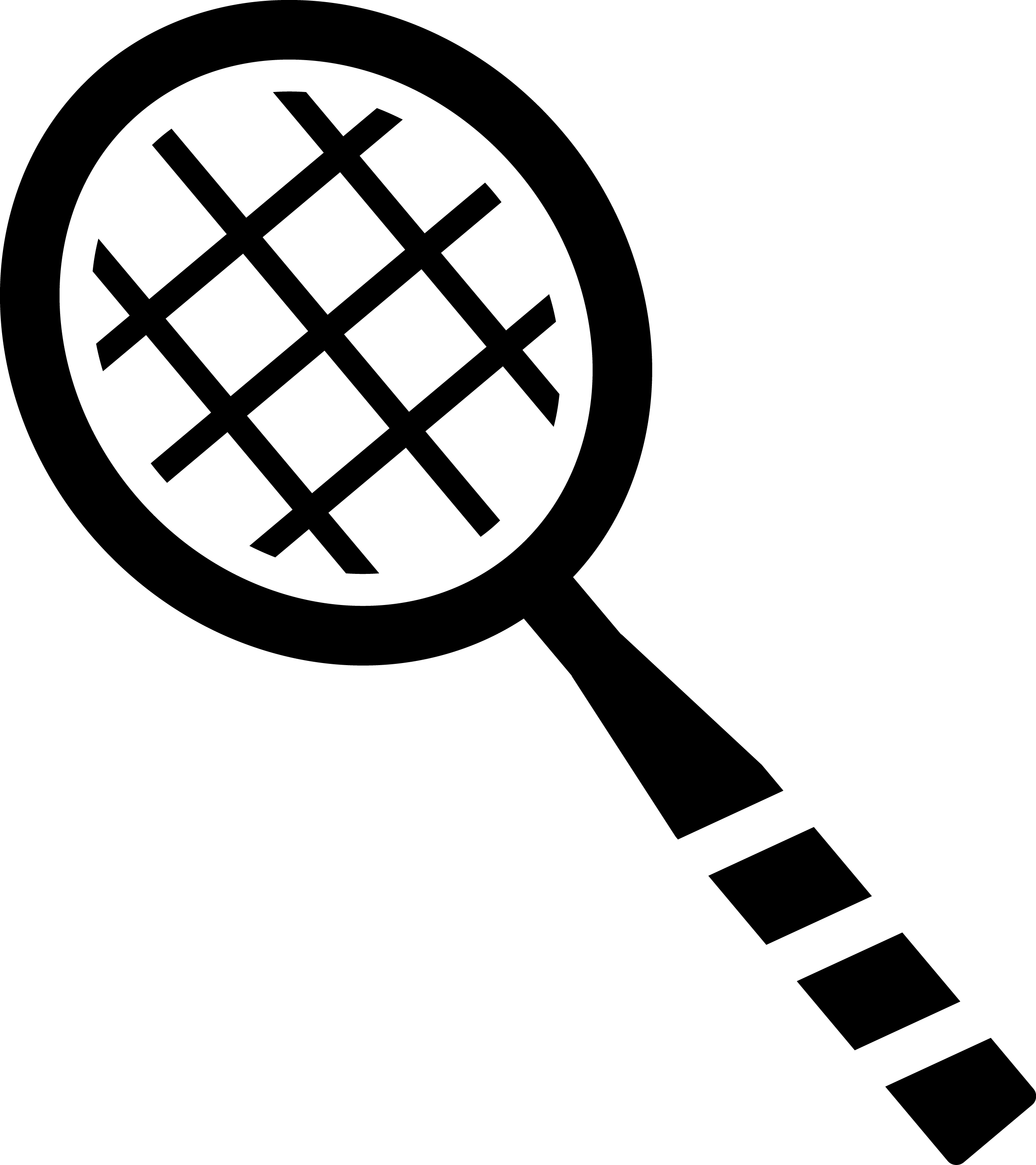



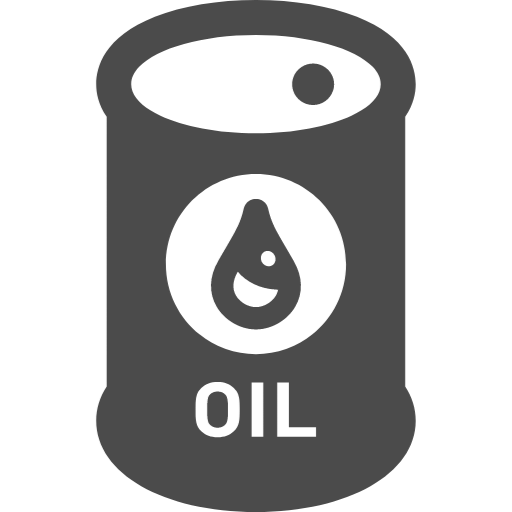
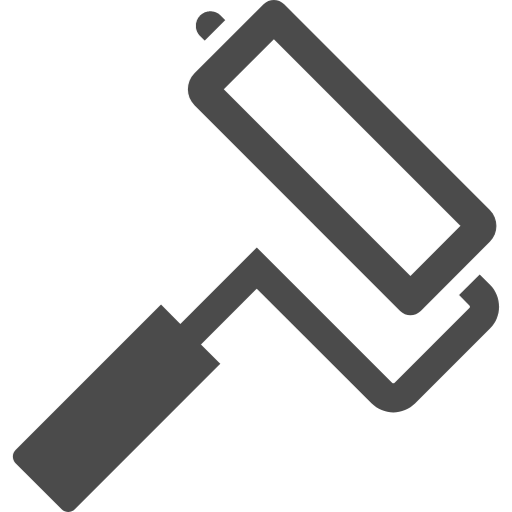
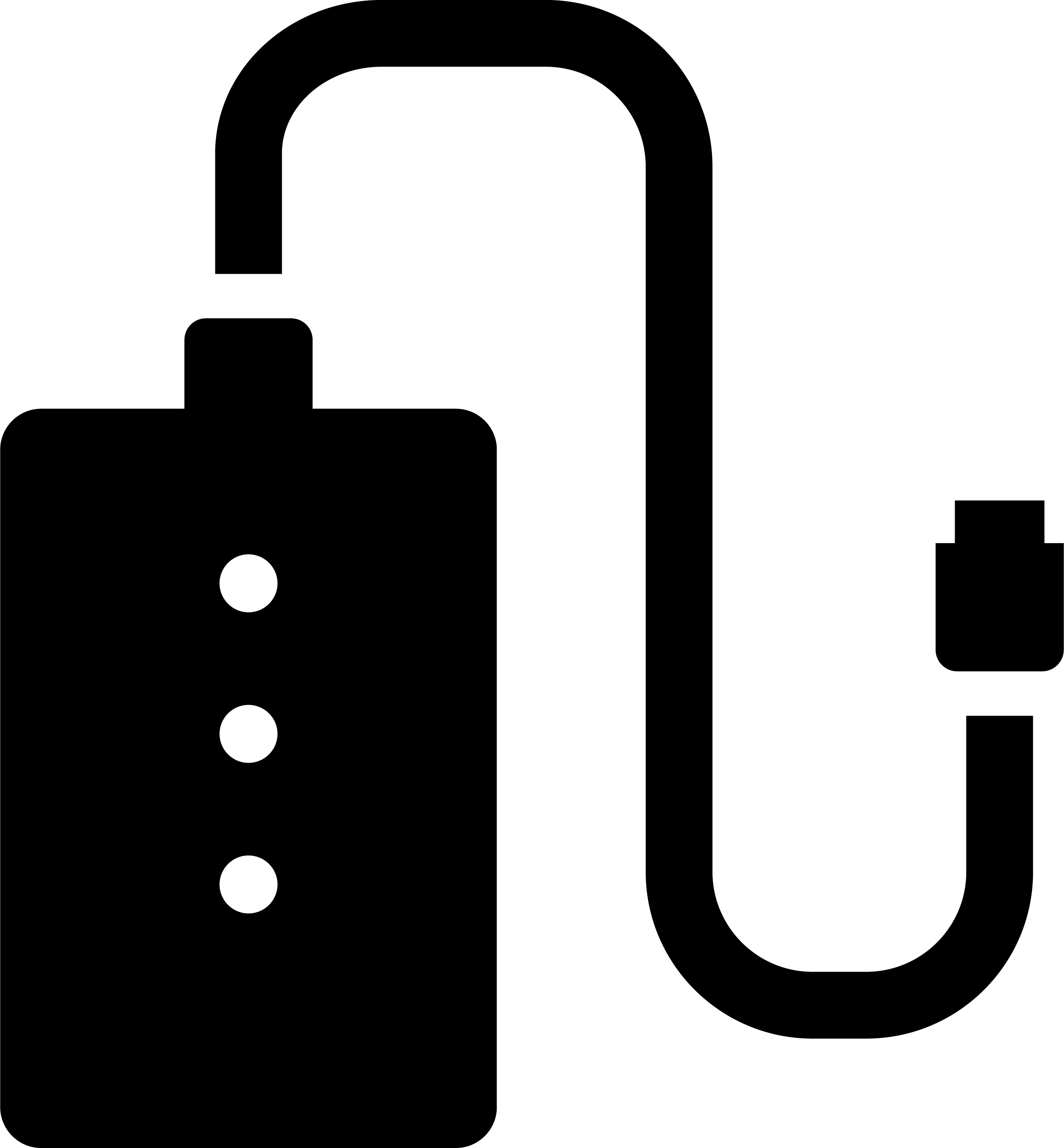
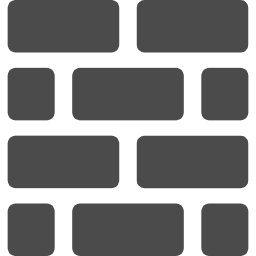
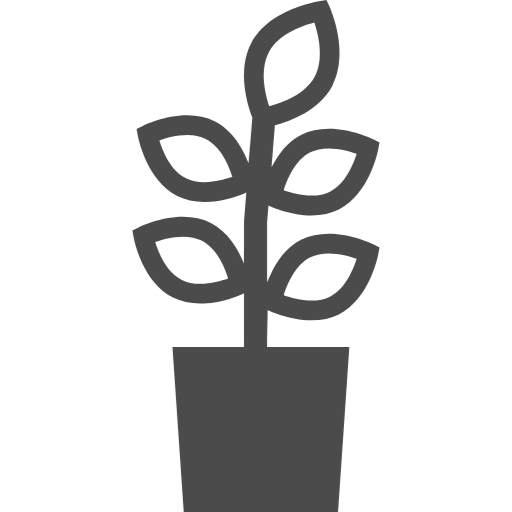

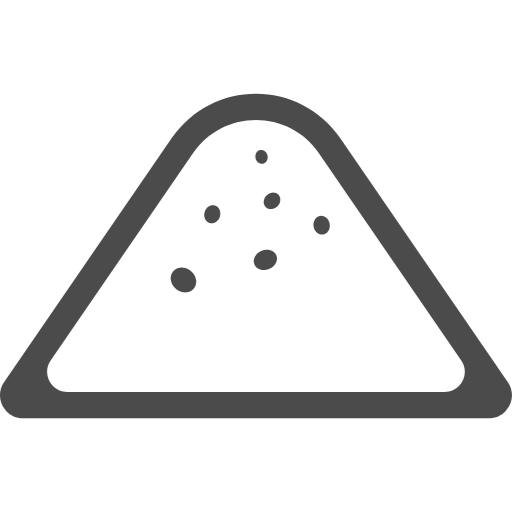
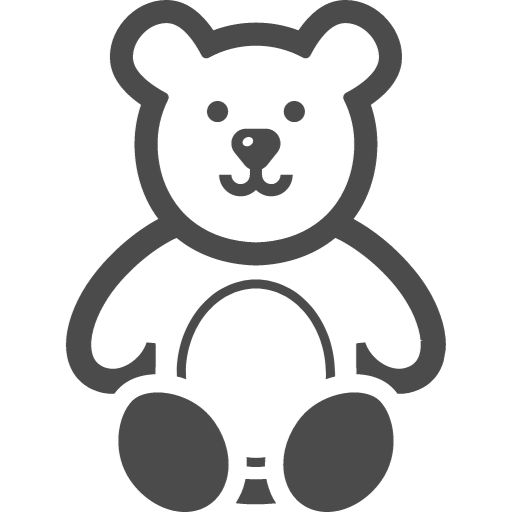
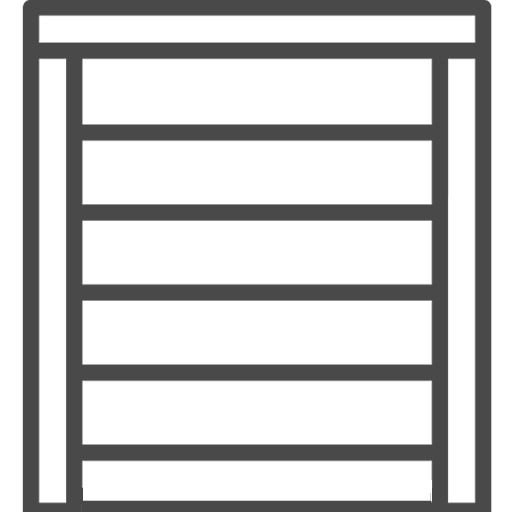



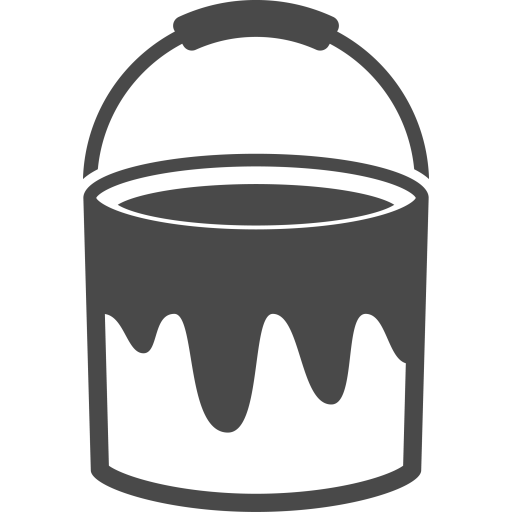
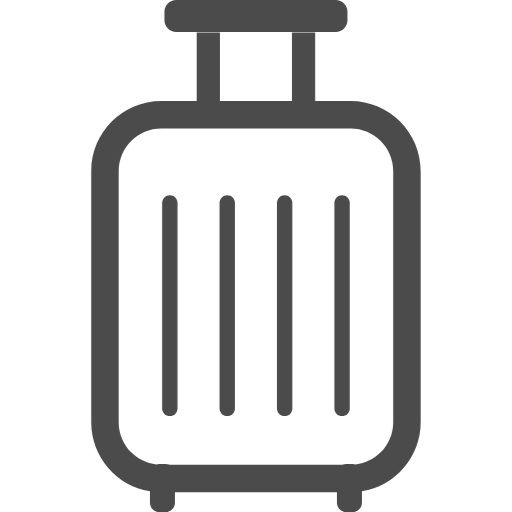
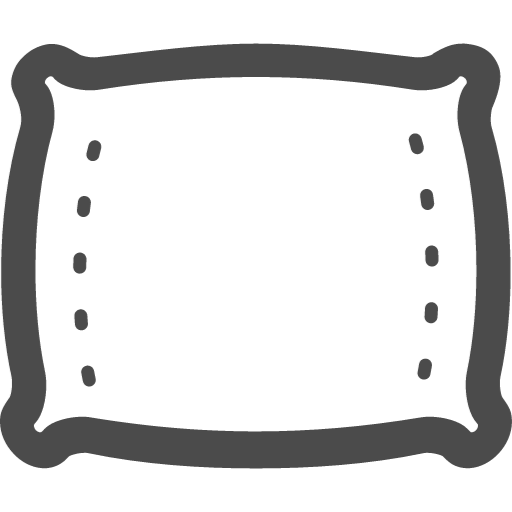
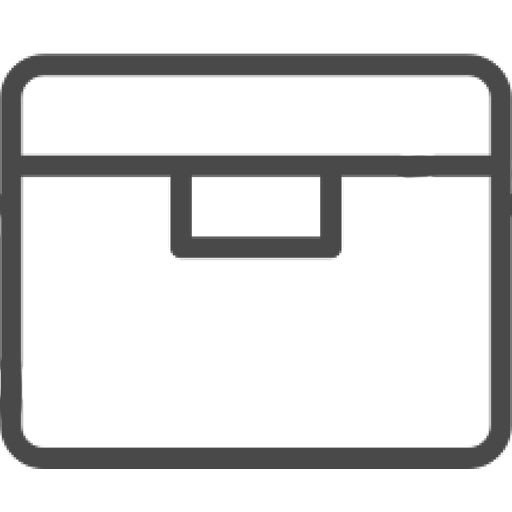

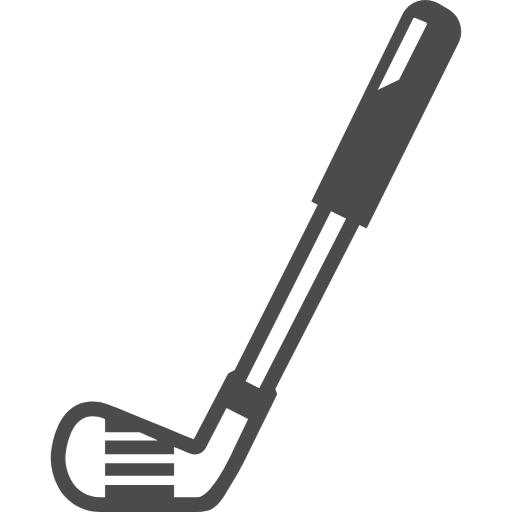
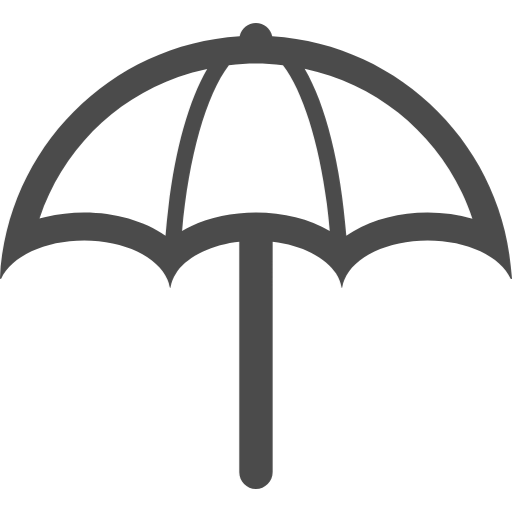

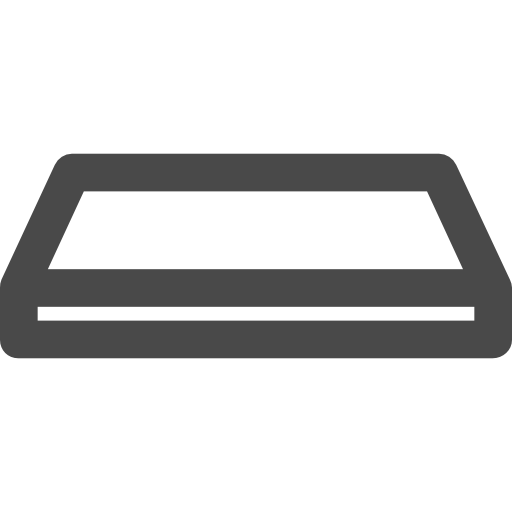

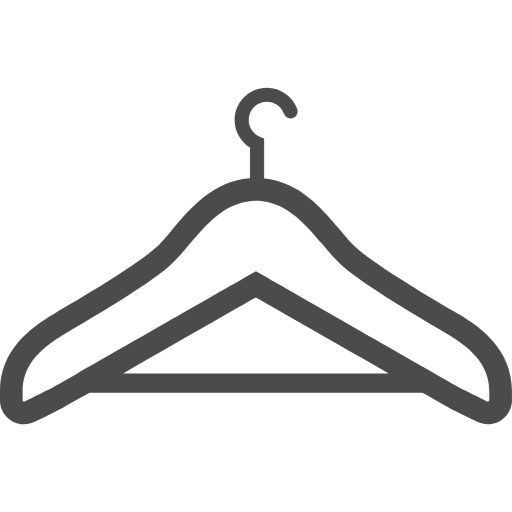
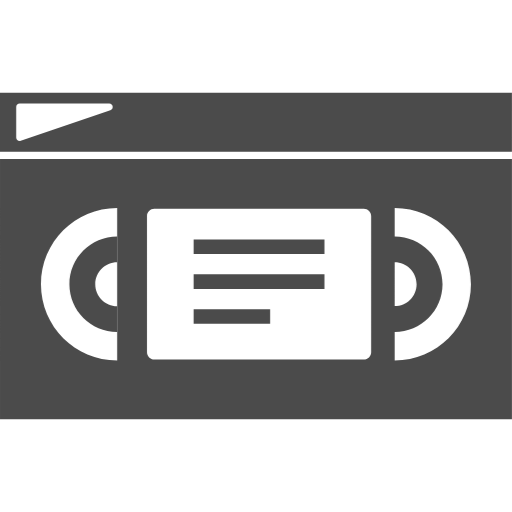
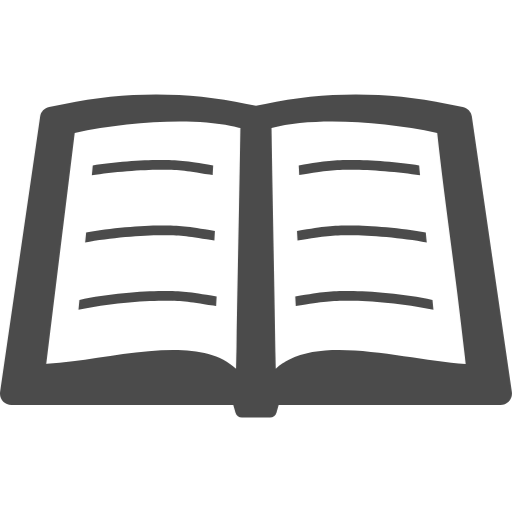
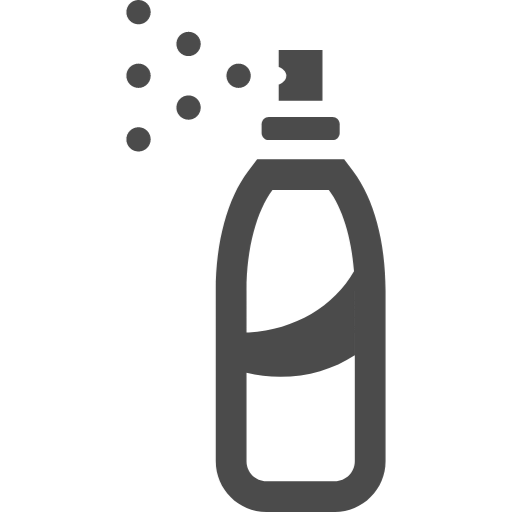
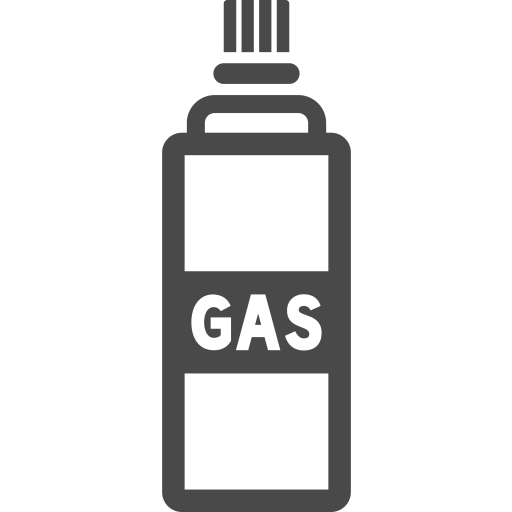
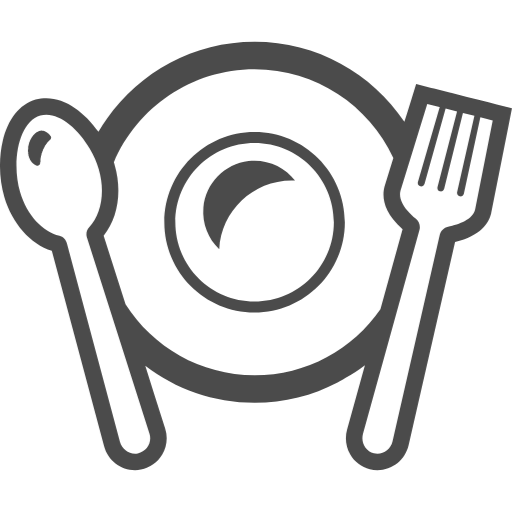
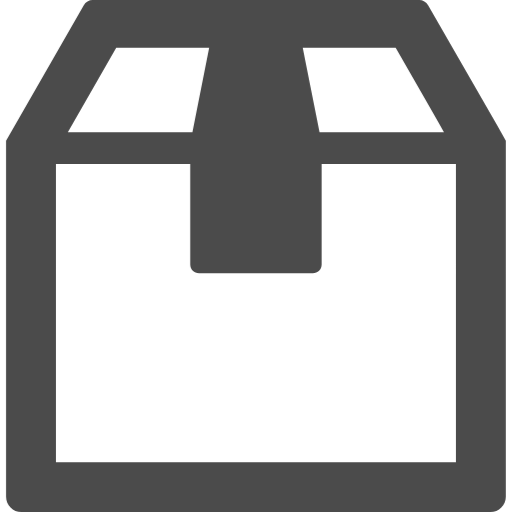
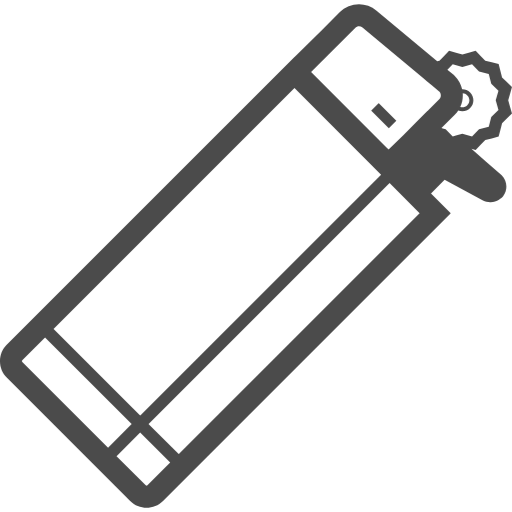
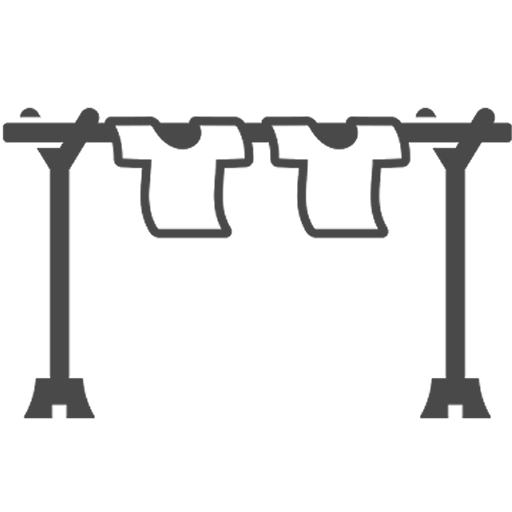
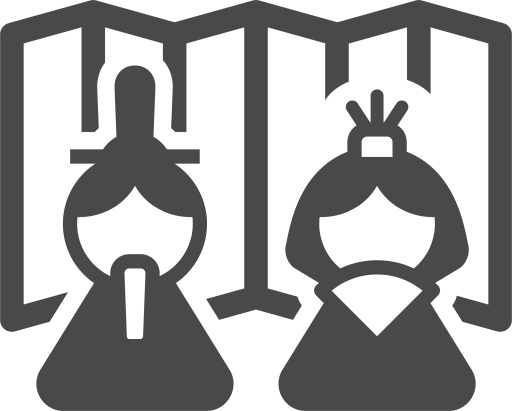
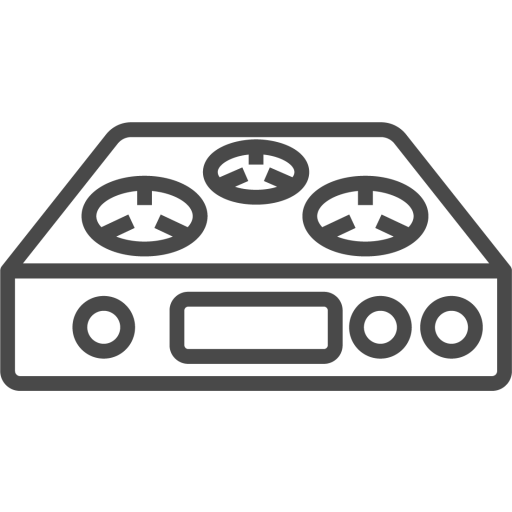
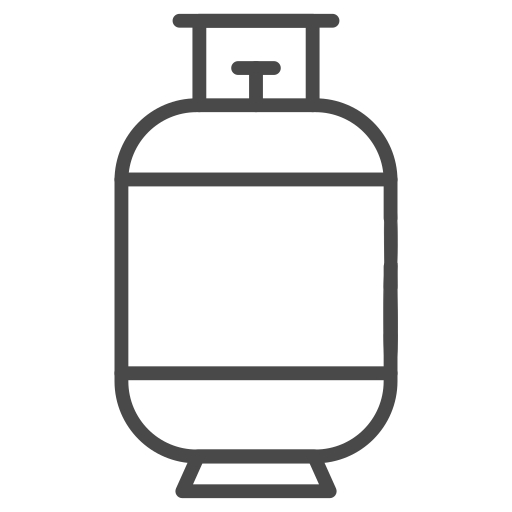
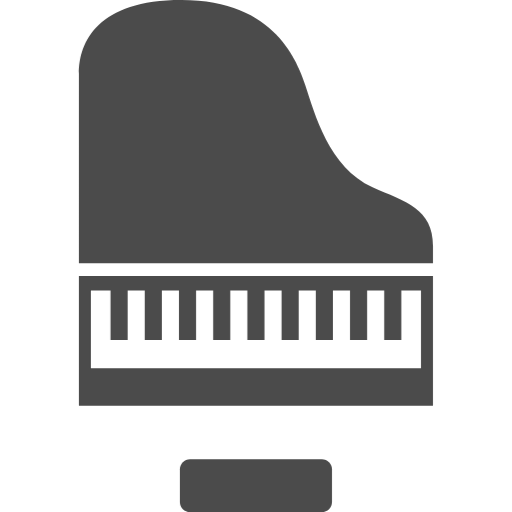
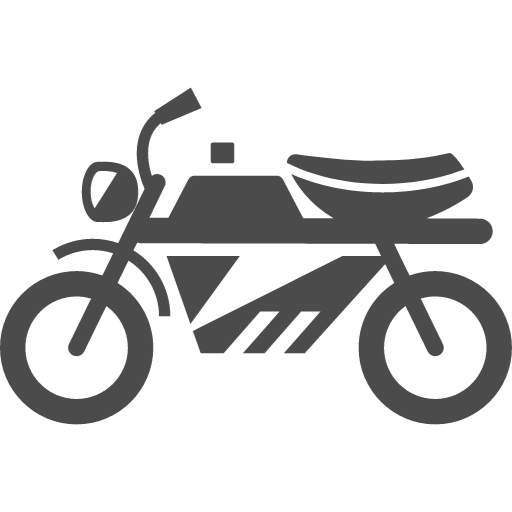
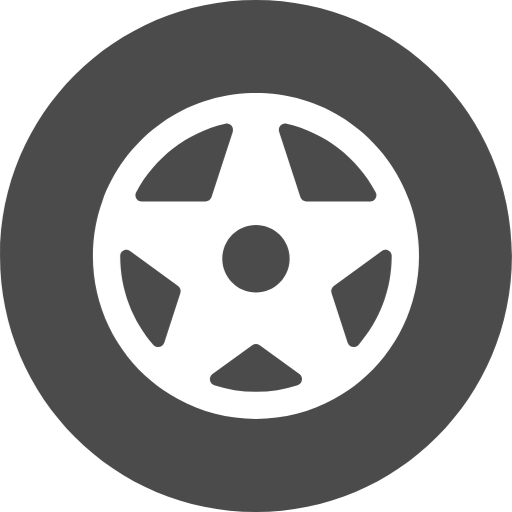
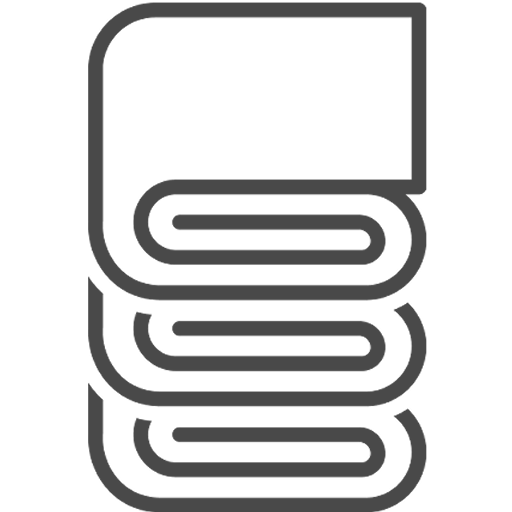






急に転勤が決まり、家族で引っ越しをすることになりました。
来てもらってから処分したものがどんどん出てきて予定よりも増えたのですが、全部引き取ってももらえたため、引っ越し準備がスムーズに行えました。